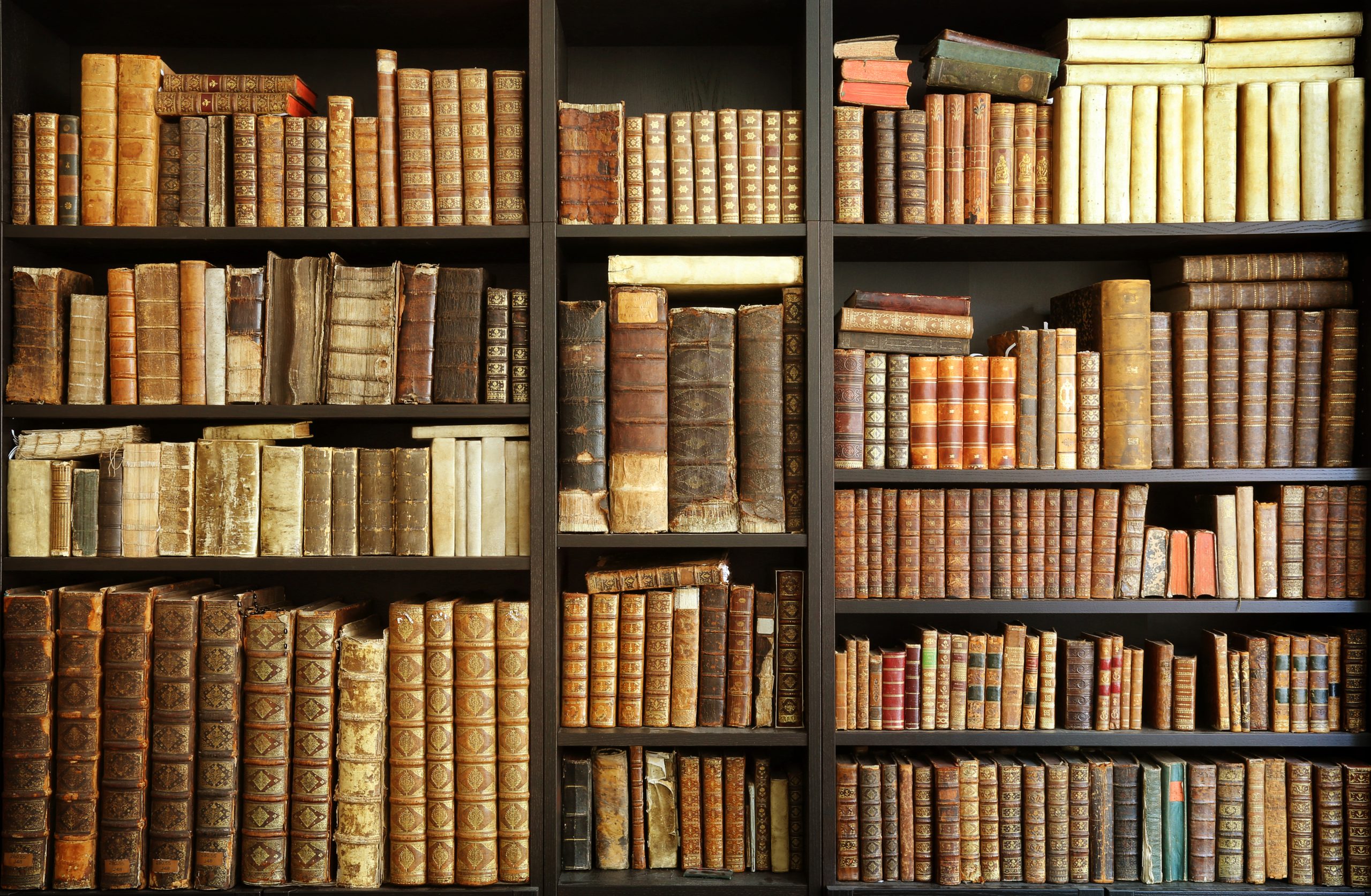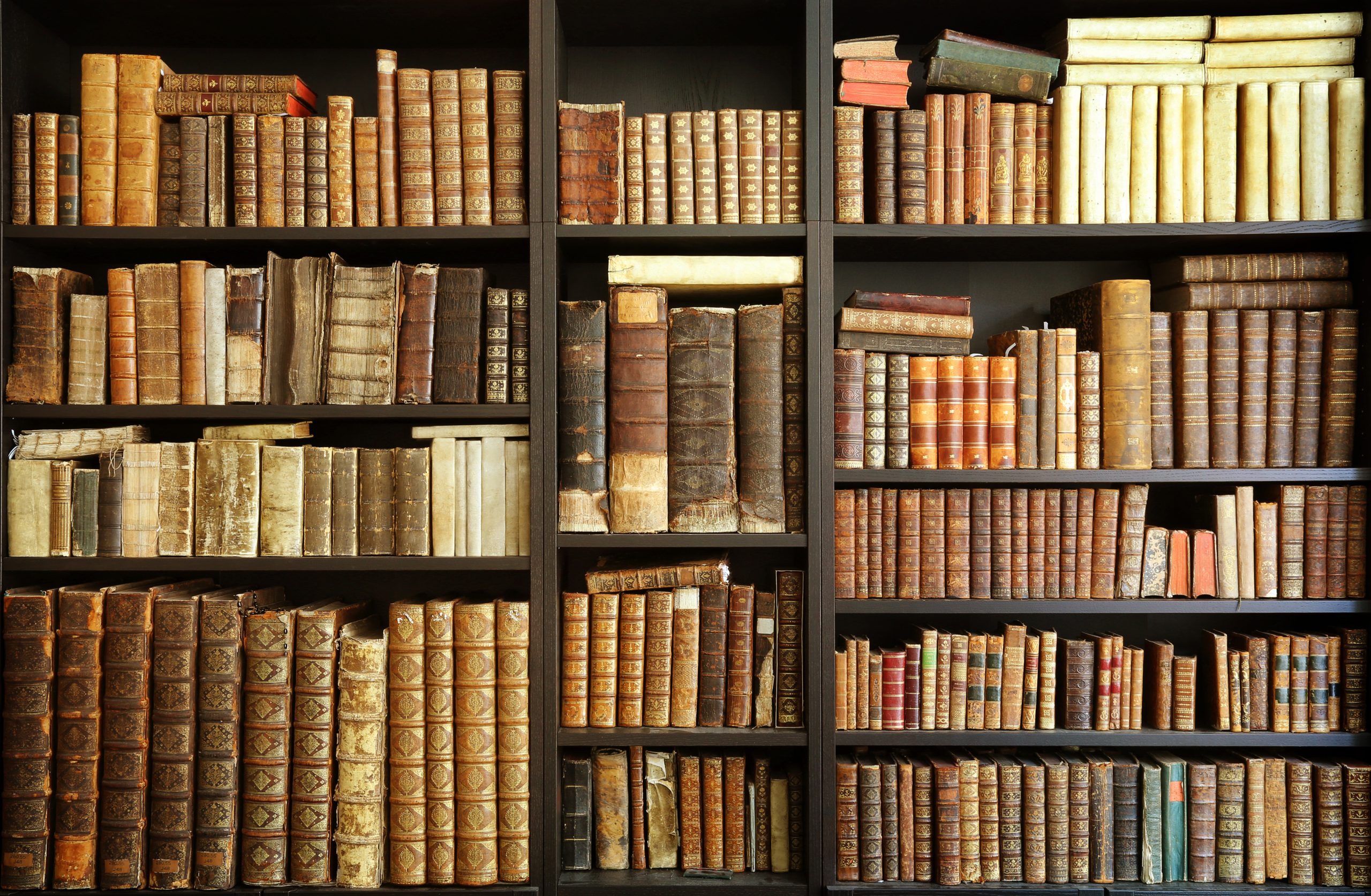出版物
イスラエル・ハマスを巡る虚偽情報とナラティブにみる国際政治の変容
要旨2023年12月8日に、法学研究科の市原麻衣子教授が執筆した記事、「イスラエル・ハマスを巡る虚偽情報とナラティブにみる国際政治の変容」が『Foresight』に掲載されました。本記事で市原教授は、イスラエルとハマスを巡る誤情報・偽情報が乱れ飛んでおり、他国政府、政党、トロール、陰謀論者など、多様なレベルのアクターが情報空間を歪め、無視できない影響を与えていると指摘しました。市原教授は、偽情報の拡散メカニズムについて、関心経済モデルが用いられ、情報の真偽や質よりも人々の関心を引き感情に訴えるコンテンツが拡散され、そうした感情に訴える虚偽のコンテンツが驚異的な速度でネット上に拡散されていると説明しました。ファクトチェックやメディアリテラシー教育の必要性が指摘される中、偽情報の出現速度がファクトチェックの速度を大幅に上回ること、人々の感情と行動を操ろうとするアクターは必ずしも偽情報ばかりを拡散するわけではないこと、影響工作を行うアクターが情報ロンダリングを行うこと等から、その効果の限界についても述べられました。最後に市原教授は、軍事力だけでなく情報が、そして当事国だけでなく様々な種類のアクターが影響力を持つ時代にあって、感情と情報に駆り立てられた人々が形成する国際政治を理解し分析するための分析枠組みが必要であると強調しました。
断片化した声 ―香港と海外における民主主義をめぐる闘い
要旨香港の状況は悪化している。活動家に対する地元当局の抑圧的な行動は増加し、抑圧の対象は国境を越えて海外の香港人にも及んでいる。活動家や支持者の逮捕、海外での法律執行の拡大から明らかなように、弾圧は自由と民主的価値の著しい侵食を象徴している。報道の自由と民主主義に関する世界的な指標における香港の順位の低下や、香港からの移民の顕著な増加は、このような悲惨な状況を反映している。しかし、時間の経過とともに、香港のディアスポラは、新しい環境における個々人の旅によって形成されるアイデンティティの変容を経験しており、コミュニティの感覚の変化が見られ、故郷の状況に対する反応には相違が生じている。この挑戦は、政治的抑圧、移住、アイデンティティ、自由と民主主義の尽きることのない探求といった、より広範なテーマを浮き彫りにしている。
ミャンマー問題、解決へ岐路
要旨2023年11月12日に、法学研究科の市原麻衣子教授が執筆した記事、「ミャンマー問題、解決へ岐路」が『信濃毎日新聞』に掲載されました。本記事は、ロシアのウクライナ侵攻に加え、イスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘が続き、同時進行で勃発する深刻な紛争による世界情勢の不安的化が懸念される中で、世界からの支援も注目も受けることのできないまま継続しているミャンマーにおける内戦に焦点を当てて論じられています。市原教授は、2021年にクーデターを起こして政権を乗っ取った国軍に対し、民主派の挙国一致政府(NUG)と少数民族が、各地で抵抗し続けており、その中でも北東部で開始された「1027作戦」の行方は今後の局面を占うことになると指摘しました。また、北東部における戦闘で生まれた多くの避難民は深刻な食料不足に直面していると述べました。このような状況下でも尚国際社会は実質的な支援を行っておらず、これ以上一般市民の犠牲を防ぐために、アジアの大国としての日本が主導して、ミャンマー問題の解決に動くべきであると強調しました。
現実の架け橋 ―VRの操作体験が、難民に対する認識にどう影響するか
要旨バーチャルリアリティ(VR)は、従来の媒体とは異なる有益な性質を持っているのだろうか?本研究では、共感誘発刺激として難民に関するドキュメンタリーを視聴した場合の効果を検証し、使用した媒体(VRとコンピュータースクリーン)に基づく効果の強さを比較する。本研究の一環として実施された実験では、VRが「イメージ他者」の視点を持つ課題に対してより効果的に共感を引き出すという証拠は得られなかった。一方で、パースペクティブ・テイキングのタイプ自体が重要な要因である可能性が示される。考察部では、実験結果を批判的文化研究(critical culture studies)の観点から国際関係の文脈におけるVR体験の批評と統合し、VR体験がどのように形成され、体験を生み出す権力構造によってどのように制限されるかを浮き彫りにする。
指数型分布族埋め込みで可視化するレコード・チャイナの言説
要旨本稿では、ベイズ機械学習の手法である指数型族埋め込みを利用して、レコード・チャイナ(Record China)から出版される記事の中にどのような言説が含まれているかを分析する。具体的には、指数型族埋め込みを利用してレコード・チャイナ記事の中の単語の意味を推定する。推定の結果、中国が自国の民主主義が優れているという主張と、アメリカこそが脅威になっているという言説が定量的に確認できた。今後データ量が拡張されれば、レコード・チャイナの言説の変化やレコード・チャイナの言説と日本の一般的なメディアの言説の違いなどの可視化も可能になるだろう。(論稿の内容はあくまでも個人の見解であり、著者が所属するディップ株式会社とは一切関係ない。)
「ボリックと彼の中国批判の蜃気楼」に関する論説 [in English]
要旨2023年10月24日、エル・エスペクタドール紙に、法学研究科博士課程在籍のサッシャ・ハニグ・ヌニェズ氏による「ボリックと中国批判の蜃気楼」と題する論説が掲載されました。この記事は、チリ大統領の普遍的人権に関する立場と、彼が中国を訪問した1週間後にスピーチを急遽変更した事例、これらの批判に報復する国々に対抗する際に中小国が負うリスクに関する内容です。ヌニェズ氏は、今日の小国には明確な立場を取る余地があり、人道的紛争においてもそうする権利を持つものの、強力な国際社会なしには不可能であると論じています。また、発展途上国は、自国の経済的潜在力、自由、国際関係に影響を及ぼす可能性のある立場を取ることに慎重な場合が多く、このことは、チリや他の国々がニカラグアやベネズエラの人権問題を批判する明確な立場をとりながら、中国の人権問題を批判しないことの説明にもなるとコメントしました。この記事は8カ国で、『ラ・ナシオン』や『エル・ピタソ』など10のメディアに掲載されています。
構造トピックモデルを用いたレコード・チャイナの分析
要旨本稿では、レコード・チャイナ(Record China)のテキストデータを使用して、運営者がどのような言説を広めようとしているのかを分析する。分析を通じて、レコード・チャイナというサイト名を持っているものの、日韓関係の負の側面に関連する記事が多いことが判明した。具体的には、慰安婦問題や旭日旗をめぐる韓国の日本に対する批判や、韓国側の行動に関連する記事が見られる。また、中国関連の報道に関しては、中国が国際協調で影響力を発揮していることや、中国の経済力と技術力の高さを強調する内容が目立つ。これはいずれも中国がアメリカと対等な関係にあるか、もしくはアメリカを越えていることを見せようとしている意図が背後にあると思われる。これはいずれも一橋大学の市原麻衣子教授の過去の別手法・別データを使った研究でも実証されたことであるため、信憑性は高いといえよう。ただし、ここで強調しておきたいのは、本記事は二年間かつ単独のメディアのみを使った分析であるため、エビデンスの強さに限界がある。例えば、分析で判明した傾向は果たしてレコード・チャイナにしか見られない傾向なのか、それとも他の日本語のメディアにも見られるような言説なのかがわからない。これは、今後データを追加することでよりはっきり識別できる。
2023年マレーシア州議会選挙 —「統一政府」の展望—
要旨2022年11月に行われた前回のマレーシア総選挙(GE15)以降、マレーシアの政治情勢は大きく変化し、特にパカタン・ハラパン=バリサン・ナショナル(PH-BN)連立政権といった新たな政治連合の形成が注目された。しかしながら、「統一政府」と呼ばれ、アンワル・イブラヒム(Anwar Ibrahim)率いるPH-BNは、マレー系有権者から確実な支持を得ることはできなかった。2023年8月に行われたマレーシア州議会選挙の結果は、PH-BNがペリカタン・ナショナル(Perikatan Nasional:PN)に精神的敗北(moral defeat)を喫したことで、このシナリオをさらに裏付けるものとなった。マレー系有権者をなだめるためにマレーシア政府がより保守的になるかどうかは、現時点では不明である。
ミャンマー紛争地への人道支援 ―現地の状況
要旨ミャンマーでは、人道支援活動の内容と効果の検証が求められている一方で、検証する方法が欠如しているという状況が長らく続いた。ヒューマニタリアン・アウトカムズ(Humanitarian Outcomes: HO)の調査は遠隔アンケートを用いて、ミャンマーで実施されている多様な人道支援活動の効果について有用な示唆に富んでいる。国際機関が展開する公式の援助プログラムが厳しい制限を受けていること、一方でインフォーマルな支援活動がミャンマーの広い範囲において既に浸透していることをHOの調査結果は示している。
アメリカにおけるESG投資の拡大と論争 ―グローバル・ガバナンスへの示唆
要旨2015年に持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)が採択されて以来、環境(Environment)、社会(Social)、コーポレート・ガバナンス(Corporate Governance)から構成されるESG投資が注目を集めている。ESG投資には、持続可能な社会を実現しようとする社会的な使命を持つ人々、リスクに敏感な投資家、学界などのさまざまなステークホルダーから関心が寄せられている。しかしアメリカではESGに反対する動きが拡大しており、共和党議員はESG関連の財務リスク管理を妨げ、ESG投資の成長を阻害しようとしている。本稿は、アメリカにおけるESG投資を巡る対立の背景と理由を探り、グローバル・ガバナンスに対する示唆を検討する。