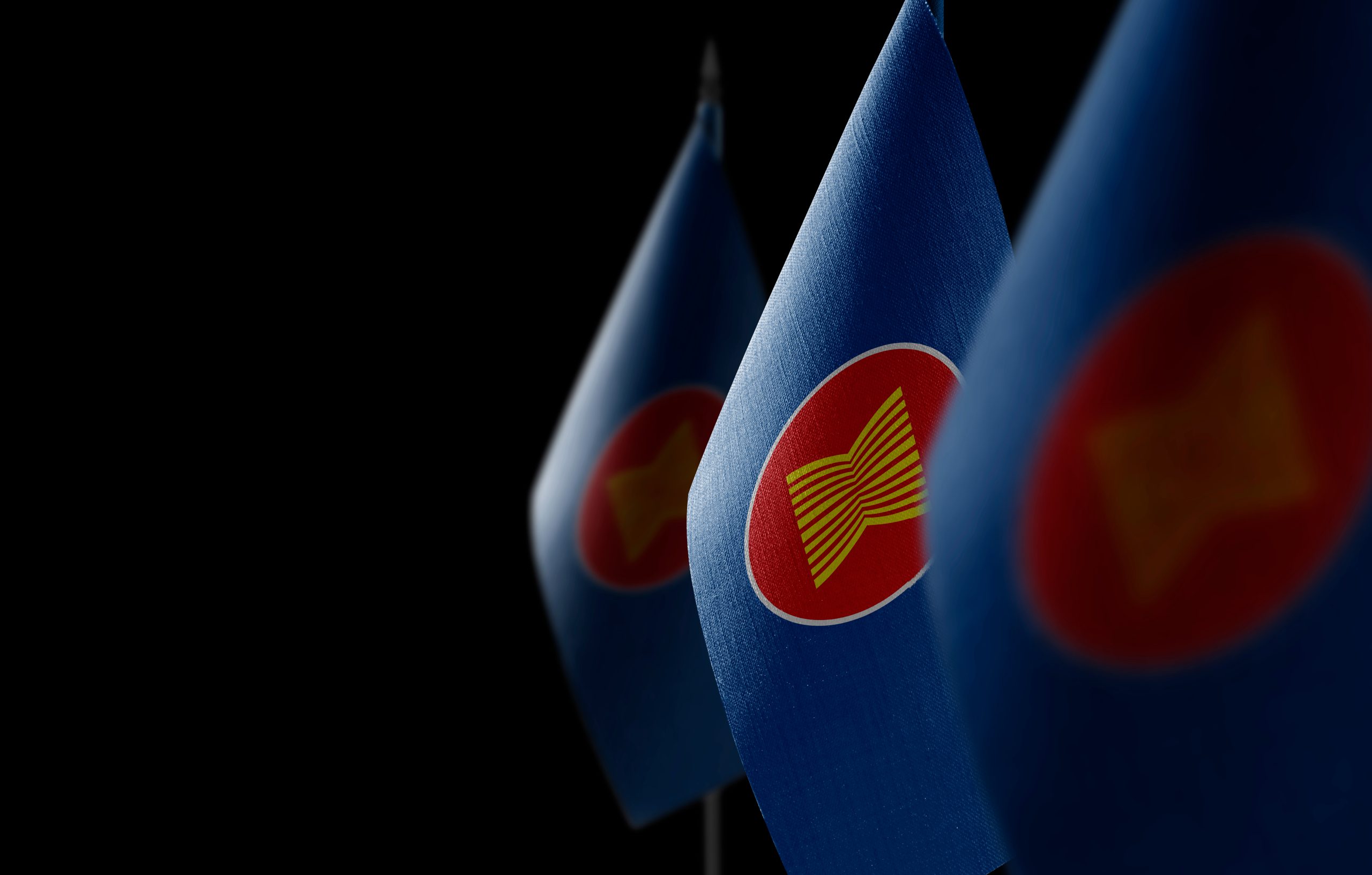GGR Issue Briefings / Working Papers
サイバー空間での影響力工作に対するアトリビューションの概要
要旨SNSにバトルフィールドを広げる影響力工作の背後には誰がいるのか、その意図は何か。本稿は、サイバー空間での影響力工作におけるアトリビューションを概説し、これらを明らかにする方途について論じる。アトリビューションに関する概念や分析のサイクル、モデルを提示し、2023年G7外相会議直前に展開されたキャンペーンを対象にモデルの実践を行う。また、意図の見積もり、データの入手、真の発信者の特定といった点から、サイバー空間に閉じた情報源を用いたアトリビューションの限界についても論じる。
選挙制度改革の試みに見る、メキシコにおける民主主義の現在地
要旨メキシコのロペス・オブラドール政権は、2022年から2023年にかけて大規模な選挙制度改革を試み、選挙関連法を改正した。法改正で規定された内容としては、有権者による選挙関連職位の選出、選挙実務を担当する職員数の削減、選挙広報に関する違反類型の限定、そして選挙違反に対する罰則の軽減などが含まれ、いずれも民主主義の根幹をなす選挙の「公平性・公正性」を脅かすものである。一方で2023年5月と6月には、連邦最高司法裁判所が違憲審査を通して法改正の無効化を宣言した。この違憲判決は、司法が恣意的な権力行使を抑制したことを示しており、メキシコの三権分立は現時点では機能しているといえる。
新型コロナウイルスワクチンを巡る偽情報への対抗ナラティブに関する一考察
要旨ワクチン躊躇/接種控え(vaccine hesitancy)が広まる原因の一つにはインターネット上での誤情報の拡散があり、いわゆる「自然派」の人々の間でSNS上での根拠のない情報のやりとりが行われていることが問題になっている。こうした懸念をいかに解消しうるかを検討するため、本稿は、偽情報を発信する主体がターゲットとしているペルソナを分析する。そしてそれに対する有効な対抗ナラティブの発信手法を検討したうえで、手法の懸念点や社会実装する上での留意点に言及する。
中国型スマートシティの地政学的挑戦
要旨スマートシティは米中が覇権を争う技術で構成された地政学的争いの場でもある。中国型スマートシティが安全を優先した統治システムであるのに対し、アメリカ企業のものは生活の質の向上、都市機能の最適化、運営コストの削減などを標榜したビジネスシステムになっている。中国型スマートシティプロジェクトは経済支援、情報化支援と一体化していることが多く、経済的、政治的に中国と深く結びついている。権威主義国や弱体化した民主主義国は政情が不安定になると中国型のスマートシティを求めるようになっており、その増加によって中国型スマートシティが増加している。世界で144件のプロジェクトが進んでおり、そこで集積された莫大なデータやネットワークは中国の戦略的優位をもたらす可能性がある。スマートシティは地政学的陣取り合戦となっているが、欧米は劣勢に立たされている。
アメリカの偽情報対策が直面している問題
要旨現在、米国下院司法委員会を中心に右派メディアや団体、評論家を巻き込んだ偽情報対策批判が広がっている。シンクタンクや大学などの研究機関、専門家個人に対してデータ提供要請、議会召喚、告訴などが行われている。米政府は直接あるいは研究機関などを通じて、SNSプラットフォームに対して検閲行為を行い、保守的言論を抑圧してきたという主張だ。2023年7月4日には連邦地方裁判所で政府の検閲を認め、政府および関係機関とSNSプラットフォームおよび研究機関との接触禁止が命じられた。すぐにこの命令は停止され、控訴が進んでいるが、一連の出来事によって、偽情報対策に慎重になるSNSプラットフォームや研究者が出て来ている。この問題は、偽情報は国内アクターが行うものの方が多く、対策もまた国内を優先しなければならない、という基本を怠ったことが原因と考えられる。
非承認国家の「民主主義」 ─その様相と規定要因─
要旨「非承認国家(unrecognized states)」は、「独立」を宣言し、国際的承認を得られないながらも事実上法的親国から独立した主体である。近年ではロシアによるジョージアやウクライナへの侵攻に際して、非承認国家やそれに類似する主体が出現し、その役割が注目されてきた。現存するその大半は競争的選挙を実施し、一部では選挙による政権交代も発生している。しかし、その多くは権威主義国からの支援で存立している上に、「民主化」しづらいとされる経済・社会的条件下にある。このため、一部の研究は、非承認国家特有の「民主化」要因が存在すると考えてきた。しかし、民主化指標によれば非承認国家の全てが民主化しているわけではなく、非承認国家の「民主化」度合いにはバリエーションがある。本論文では、非承認国家の政治体制の現状と関連する先行研究をレビューし、その課題を指摘した上で、新たな仮説の可能性を提起する。
ASEAN 5項目合意実行の失敗
要旨ミャンマーのクーデター指導者とASEAN首脳は、5項目について合意した。また、死者数、拘束者数、国内避難民数についても合意した。しかし、ミャンマー国軍、民族武装集団、人民防衛軍間の紛争は激化している。また、ASEANの一部の首脳は、ミャンマー国軍が人道的支援を国民に届かせないようにしていることから、ミャンマー国軍による合意履行プロセスは失敗だと言える。そのため、国際機関は、緊急に必要としている人々を支援するために声を上げた。合意から一年半が経過した今、ASEAN首脳は国軍による実施状況を検証し、ミャンマー国民の利益を尊重した有意義な行動を取るべき時である。
ロシア・ウクライナ戦争でのロシアによる核の威嚇 -中国はどのように捉えたのか-
要旨中国は、ロシア・ウクライナ戦争でのロシアの核による威嚇とその結果を受け、自国の核兵器の新たな役割として「他国の直接的な軍事介入の抑止」に注目するとともに、自らの「戦略抑止」の方法に対する自信を深めた。これにより、台湾有事が発生した場合、中国が他国の直接的な軍事介入を抑止するため、核の威嚇を実行に移す可能性が懸念される。
2023年タイ総選挙 ―野党の台頭
要旨タイの総選挙が5月14日に実施される。クーデターを起こしたプラユット・チャンオチャ将軍(General Prayut Chan-o-cha)が率いる親軍政権に固執するのか、それとも別の道を歩むのか、タイ国民が決断するときが来た。親軍政党を優遇する非民主的な憲法にもかかわらず、最近の傾向では、2大野党であるプアタイ党(Pheu Thai Party)とタイ前進党(Move Forward Party)が地滑り的に勝利し、親民主的な連立政権が誕生する可能性がある。プアタイ党は、これまでの記録や最近の世論調査から、総選挙のたびに最多議席を獲得していることから、向かうところ敵なしといえる。今度の選挙でも勝利する可能性が高いと考えられる。一方、タイ前進党とその党首であるピター・リムジャルーンラット氏(Pita Limjaroenrat)の人気は、明確な政治姿勢、変化をもたらすことを望む印象的な政策、政策論争での卓越したパフォーマンスによって急上昇している。このような理由から、タイを軍事政権の遺産から救う、親民主的野党による新政権が誕生する可能性がある。
チリにおける憲法改正の否決より、民主的プロセスと裏切られた期待について何が学べるか?
要旨2022年9月、チリの有権者は、1年以上かけて起草され、三権分立などの自由民主主義の基本的要素を制限する新憲法案を、62%の反対をもって否決した。2023年11月にはチリで新たな国民投票が実施される予定であり、さらに他の多くの国々でも憲法改正が検討されている。こうした経緯を踏まえ、本稿では以下の2つの問いについて論じる。第一に、改憲プロセスの動向からどのような教訓が得られるのか。そして第二に、チリにおける憲法改正否決の主な理由は何なのか。これらの問いに答えるために、本稿ではまず、チリ国民によって共有されているナラティブを概観する。そして憲法改正が失敗に終わった背景、すなわちコミュニケーション不足や国民の信頼の喪失、そして憲法改正案に対する失望について分析する。