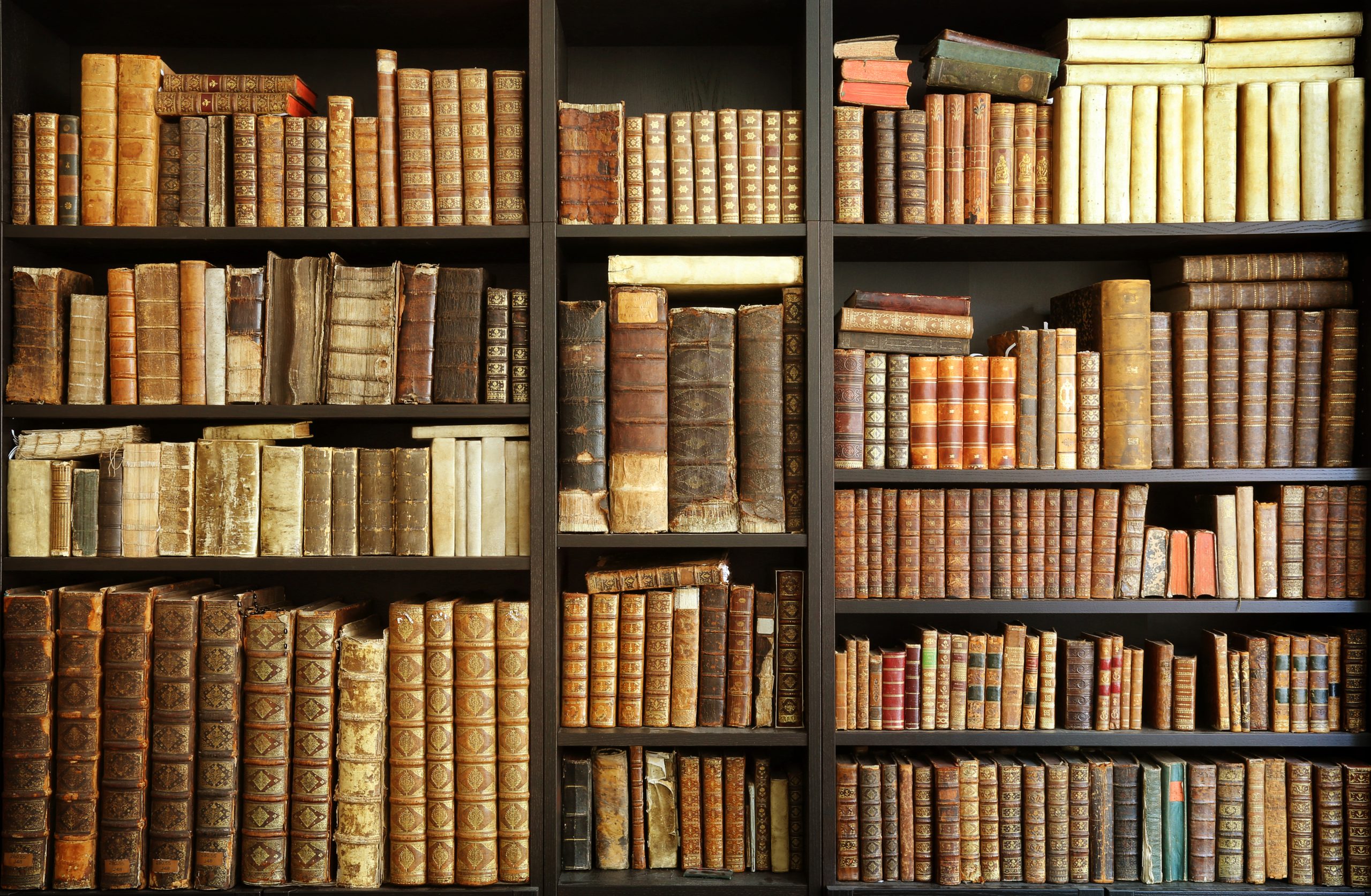出版物
民主主義・人権プログラム
チリ−中国FTA -銅のモノカルチャー、限定される多角化、隠れた依存関係 [in Spanish]
出版日2024年8月5日
民主主義・人権プログラム
中国共産党が狙った日韓・日台関係へのくさび ―第三国の社会を標的にする影響工作
出版日2024年4月1日
民主主義・人権プログラム
ハシナ最後の抵抗 -クオータ運動、学生の蜂起、バングラデシュ民主主義の未来
出版日2024年11月13日
要旨バングラデシュは、16年間シェイク・ハシナに統治されてきた。その間、不正投票がはびこり、有権者は脅迫され、反対派は暴力的に弾圧されたことで、民主主義が損なわれてきた。しかし、学生を中心とするクオータ制度をめぐる反対運動と、それに続く蜂起によって、流れは変わり始めた。最終的に、ハシナは政権から追い出され、軍主導の暫定政権が樹立された。このような変化にもかかわらず、バングラデシュは依然として民主主義を模索しており、ハシナの長期間にわたる非民主的な統治からの回復に苦闘している。
民主主義・人権プログラム
民主主義・人権プログラム
日本の国連政策に見る人権外交 ―人権規範の役割と多国間主義の態様変化―
出版日2024年8月1日
民主主義・人権プログラム
国際秩序に背を向けた民主主義 ―世界関与への矜持と戦略を取り戻せるか [in English]
出版日2024年6月3日
民主主義・人権プログラム
偽情報時代における日本の偶然の回復力 [in English]
出版日2024年5月9日
民主主義・人権プログラム
中国とロシアに見るデジタル影響工作の生態系
出版日2024年5月21日
民主主義・人権プログラム
ジョージア安定化へ行動を
出版日2024年5月12日
民主主義・人権プログラム