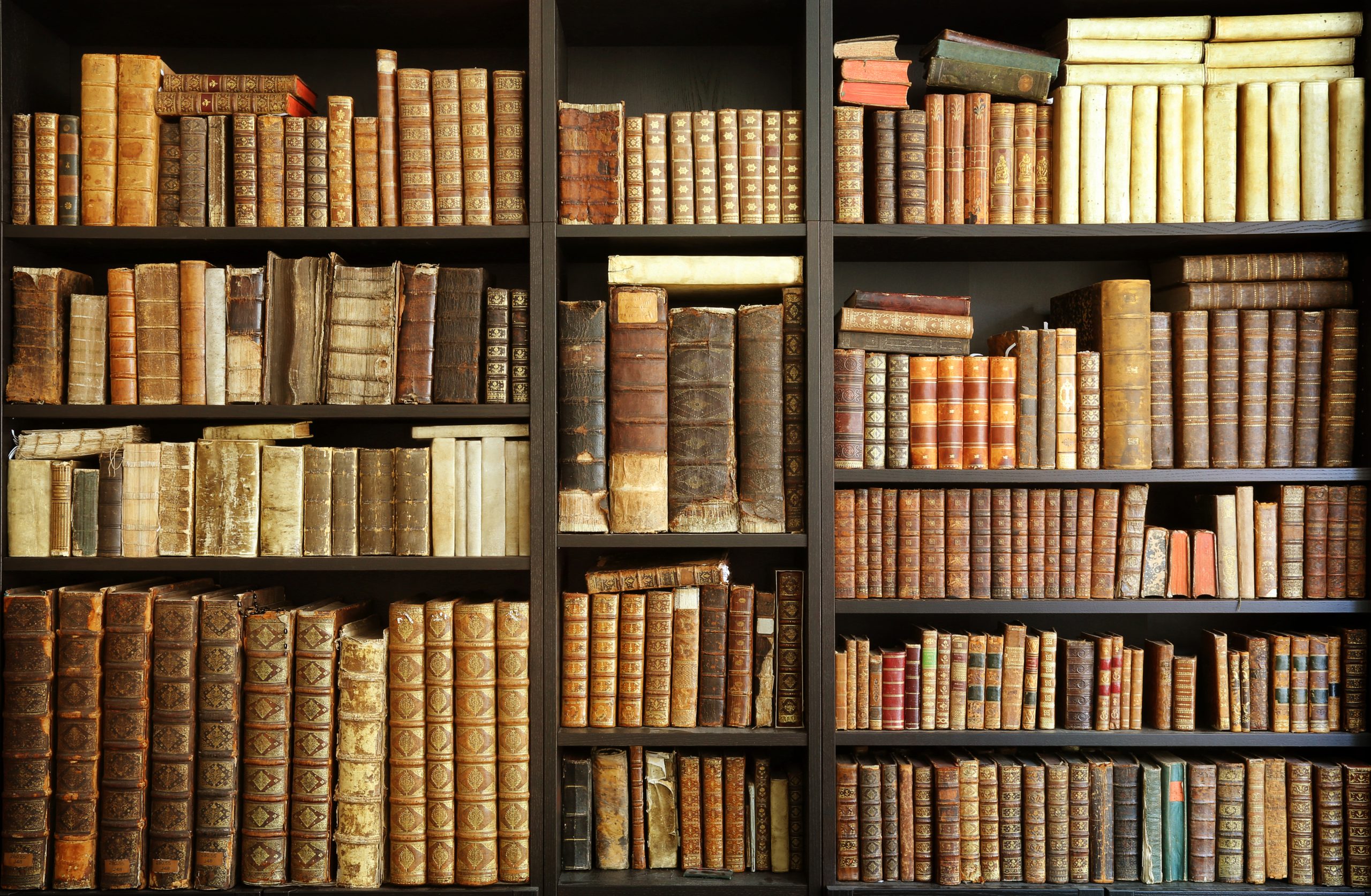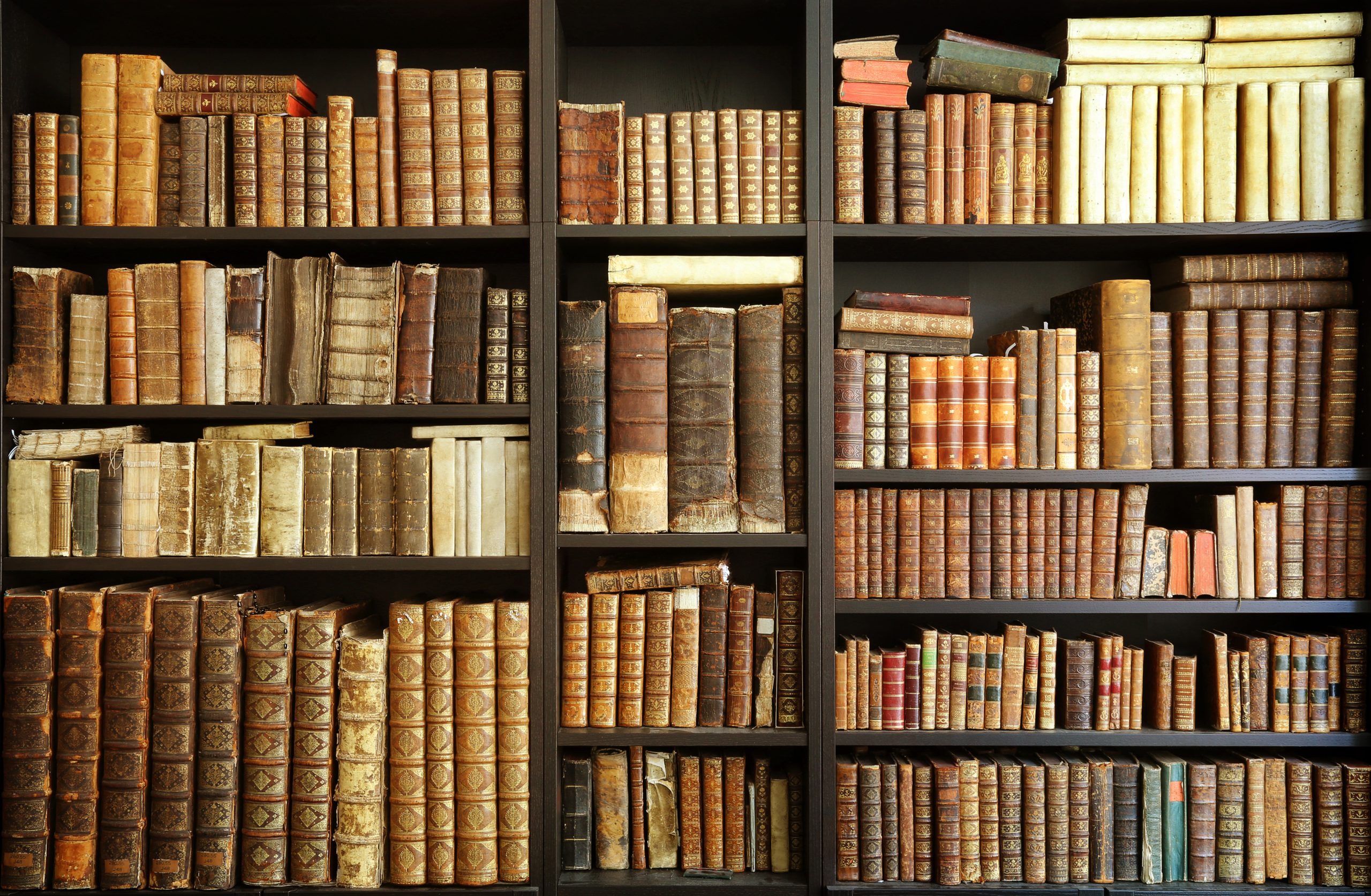出版物
軍事力で平和を維持できるか
日本の軍備管理・不拡散政策
止まらない中国の核軍拡 日本は「非核3原則」を守れるのか
止まらない中国の核軍拡 日本は「非核3原則」を守れるのか
衛星画像を用いた中国の戦略核戦力増強の現状に関する分析
要旨2024年3月4日に、法学研究科の秋山信将教授が共同で執筆した論文、「衛星画像を用いた中国の戦略核戦力増強の現状に関する分析」が『東京大学先端科学技術研究センター創発戦略研究オープンラボ』に掲載されました。本論文では、中国が内陸部で進めている大陸間弾道ミサイル基地建設の状況を分析し、その進捗状況を明らかにするとともに、グローバルな軍事バランスに及ぼす影響について考察しています。まず、新疆ウイグル自治区の哈密におけるサイロ建設状況について、衛星画像を利用して分析した結果、サイロに大陸間弾道ミサイルが装填されているかは明らかにならなかったものの、ロシアに類似するサイロ発射型の開発が推測できると指摘しました。さらに、中国の核戦略の変化について、2030年代半ばにおいては、核優越、あるいは最大限抑止の確立が中国の目標に含まれている可能性は排除できないと論じました。最後に、中国の核態勢と米中の軍事バランスについて5つのシナリオを提示しながら考察し、地域レベルでも相互抑止を制度化するような軍備管理の成立の重要性を強調しました。
グローバル・ヘルスレジームにおける調査・検証権限の制度的考察
要旨2023年11月25日、法学研究科の秋山信将教授が執筆した論文、「グローバル・ヘルスレジームにおける調査・検証権限の制度的考察」が『国際政治』第211号「ヘルスをめぐる国際政治」に掲載されました。本論文では、国家主権が前面に押し出されてくる国家安全保障上の脅威に近い感染症パンデミック危機の中で、国際レジームの提供する価値と規範の実効性が担保されるための要因が分析されています。秋山教授はまず、国際原子力機関(International Atomic Energy Agency)の包括的保障措置協定の追加議定書や化学兵器禁止条約(Chemical Weapons Convention)のチャレンジ査察の事例を取り上げ、国家主権を制約する制度の導入が可能になる要因として、技術的実現可能性、社会的要請、政治環境、主権国家の裁量が制度的、政治的に可能になっていることを整理しました。次に、国家と世界保健機関(World Health Organization)の関係性の観点から、国際保健規則(International Health Regulations)の改正とパンデミック時の情報共有及び報告をめぐる制度上の問題を論じています。最後に、公衆衛生分野における国際レジームを通じた感染症対策の実効性向上のために、求められる国際機関の役割と国家主権の対立を乗り越えるための方策について提言しています。
日本はどのように拡大抑止の信頼性を強化すべきか? [in English]
要旨2023年10月16日に、国際・公共政策大学院院長の秋山信将教授が執筆した論文、「日本はどのように拡大抑止の信頼性を強化すべきか?」が日本国際問題研究所のAJISS-Commenttaryに掲載されました。本論文では、ロシアのウクライナ侵攻を経て、拡大抑止への信頼が揺らぐ国際情勢において、日本の拡大抑止の信頼性を高める努力としての「拒否的抑止」にとどまらない「懲罰的抑止」能力の構築、脅威削減のための外交的イニシアティブを追求することの重要性に関して考察しています。秋山教授は、日本の安全保障にとって米国との拡大抑止体制の強化が不可欠であることは当然だが、今必要なのは、日米が他のパートナー諸国と協力して、抑止体制を構成する戦略資産を構築するために迅速に実施できる行動計画、脅威の状況に応じて最適化された戦略資産を効果的に運用するための日米同盟の調整メカニズム、そして確固たる政治的基盤であると指摘しました。また、東アジアの地域レベルで中国による強圧的な行動の余地を増やさないようにするため、日米をはじめとするパートナー諸国が、中国や北朝鮮に対して緊密に連携した統一的なシグナルを発信することが不可欠であり、それと同時に、危機の安定を確保し、将来の軍備管理につながる信頼を構築するために、中国や北朝鮮との戦略的対話を通じた外交努力が必要であると述べました。
核軍備管理・軍縮の新しいフェーズ
要旨2023年7月31日に、国際・公共政策大学院院長の秋山信将教授が執筆した論文、「核軍備管理・軍縮の新しいフェーズ」が『外交』に掲載されました。本論文は、大国間の軍備管理に必要なレジームの新たな構造計算の構成要素の分析と、その帰結としての核軍縮の基盤を築く方法について考察しています。秋山教授は、冷戦期に構築された軍備管理レジームにおける関連国の目的とレジームを維持させた諸原理がもはや十分に機能していないと指摘しました。その原因として、軍備管理レジームの当事国間の政治的関係の最低限の見解の一致、すなわちガードレールに対して見解の乖離が発生していると論じました。さらに、中国の台頭により、技術的・量的な軍備拡大と中国が有する軍備にかかわる戦略・戦力の不透明性故に、軍備管理レジーム再構築に複雑性が増したと説明しました。これらの問題を目前に、秋山教授は大国間の核政策における原理的見解の差異を解消し、そして外交や経済をも組み合わせて危機を管理する統合軍備管理が必要であると述べました。
(私の視点)広島ビジョンの意義:首脳らを包摂、被爆地の力 秋山信将
要旨2023年6月2日に、朝日新聞にて国際・公共政策大学院長の秋山信将教授の論考「(私の視点)広島ビジョンの意義:首脳らを包摂、被爆地の力」が掲載されました。本記事では、G7サミットが核軍縮において持つ意義が論じられました。秋山教授は、G7広島サミットにおける主要な2つのキーワードであった規範と責任を核軍縮の観点から分析しました。秋山教授は、G7参加国による核戦争反対への共同声明は、戦後長らく守られてきた核兵器不使用の規範の重要性を再確認していると説明しました。また、責任に関しては、国民の安全を守る責任と「核なき世界」を実現する責任、この2つの責任が政治指導者にあることが確認されたと論じました。最後に、秋山教授は広島サミットの経験が直ちに政策に反映されるとは信じがたいが、規範と責任の自覚がいずれ大きな力になるはずと評価しました。
広島G7サミットと核軍縮―重要な議論、さらに求められることは(英語)
要旨2023年5月23日、国際・公共政策大学院長及び法学研究科教授でGGR研究員の秋山信将教授の論考「広島G7サミットと核軍縮―重要な議論、さらに求められることは(原タイトル:The Hiroshima G7 Summit and Nuclear Disarmament: Essential talks were held, but more is now needed)」が、ザ・ディプロマットに掲載されました。秋山教授は、G7サミットで発表された「核軍縮のための広島ビジョン」の位置づけやG7首脳が被爆地に立った意義について論じています。秋山教授は、核軍縮をライフワークとしてきた岸田首相が、広島でサミットを開催した意義を評価しました。さらに「広島ビジョン」は、厳しい国際環境にもかかわらず核軍縮を前面に立てたと論じ、既存の枠組みに則るだけでなく、透明性の向上といった点における新しいイニシアチブを打ち出したと指摘しました。最後に、グローバルガバナンスや核なき世界におけるG7の役割を強調し、国際社会は今回のサミットをより実質的な措置を実行するためのきっかけとするべきだと述べました。