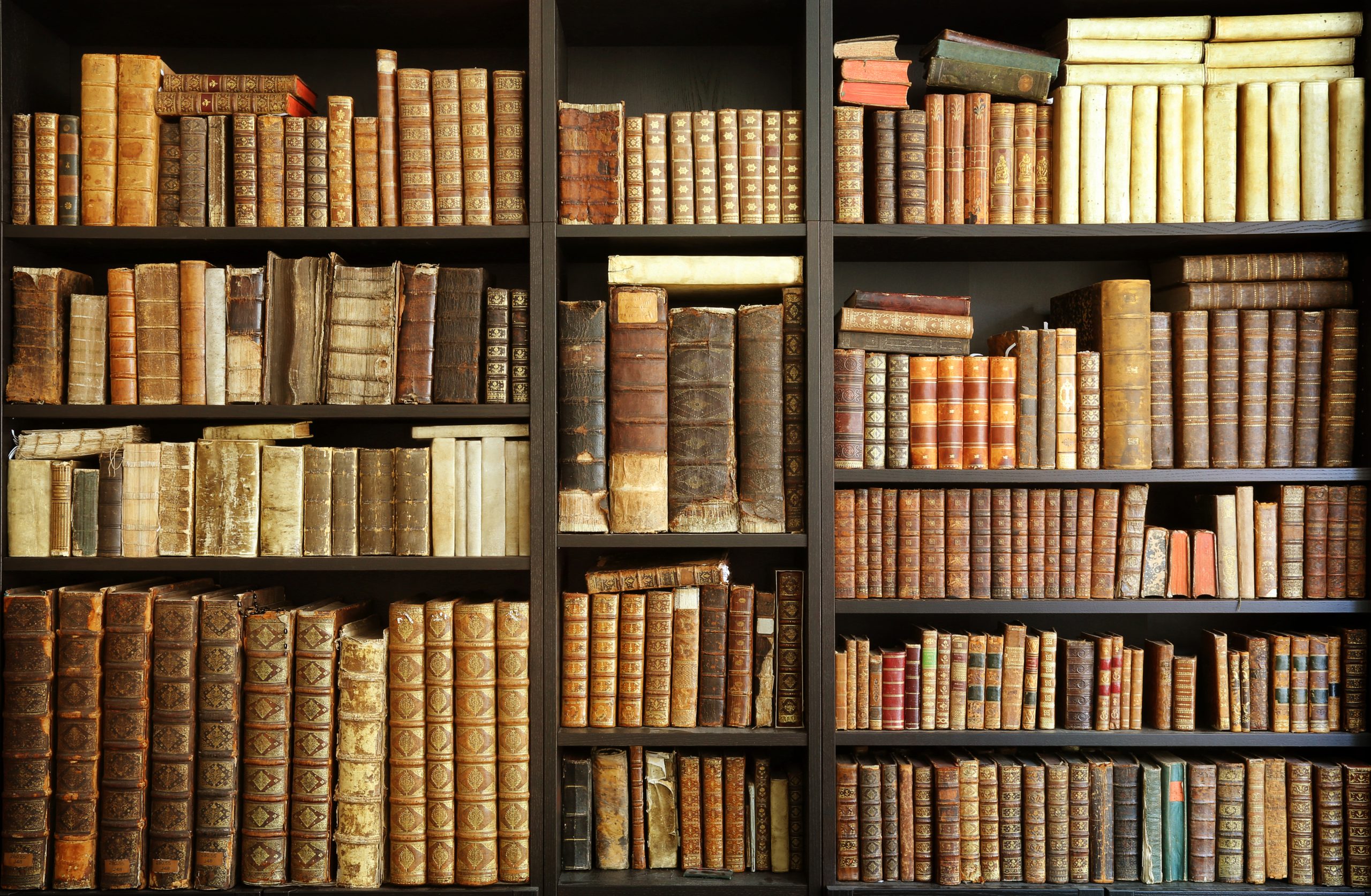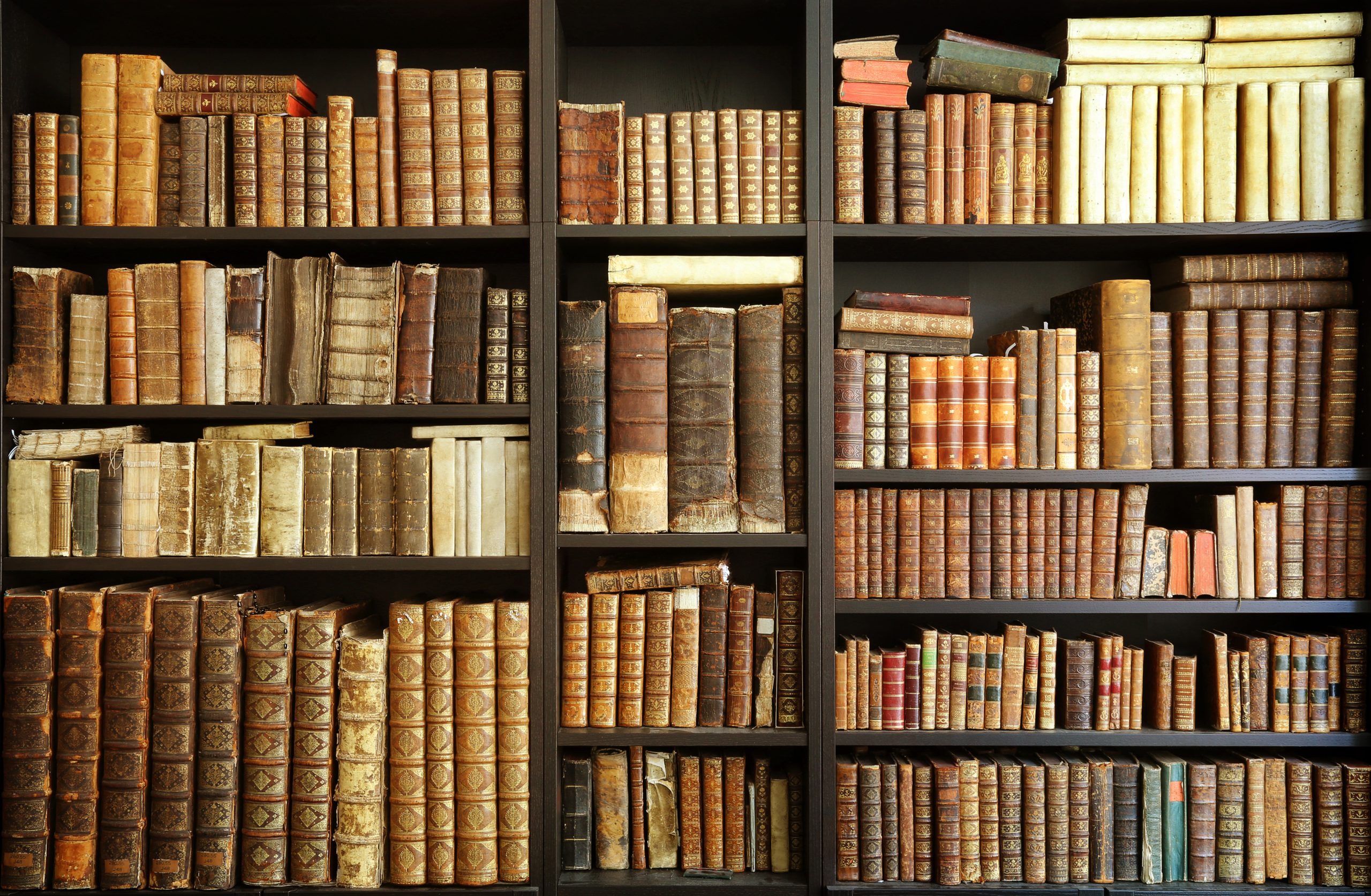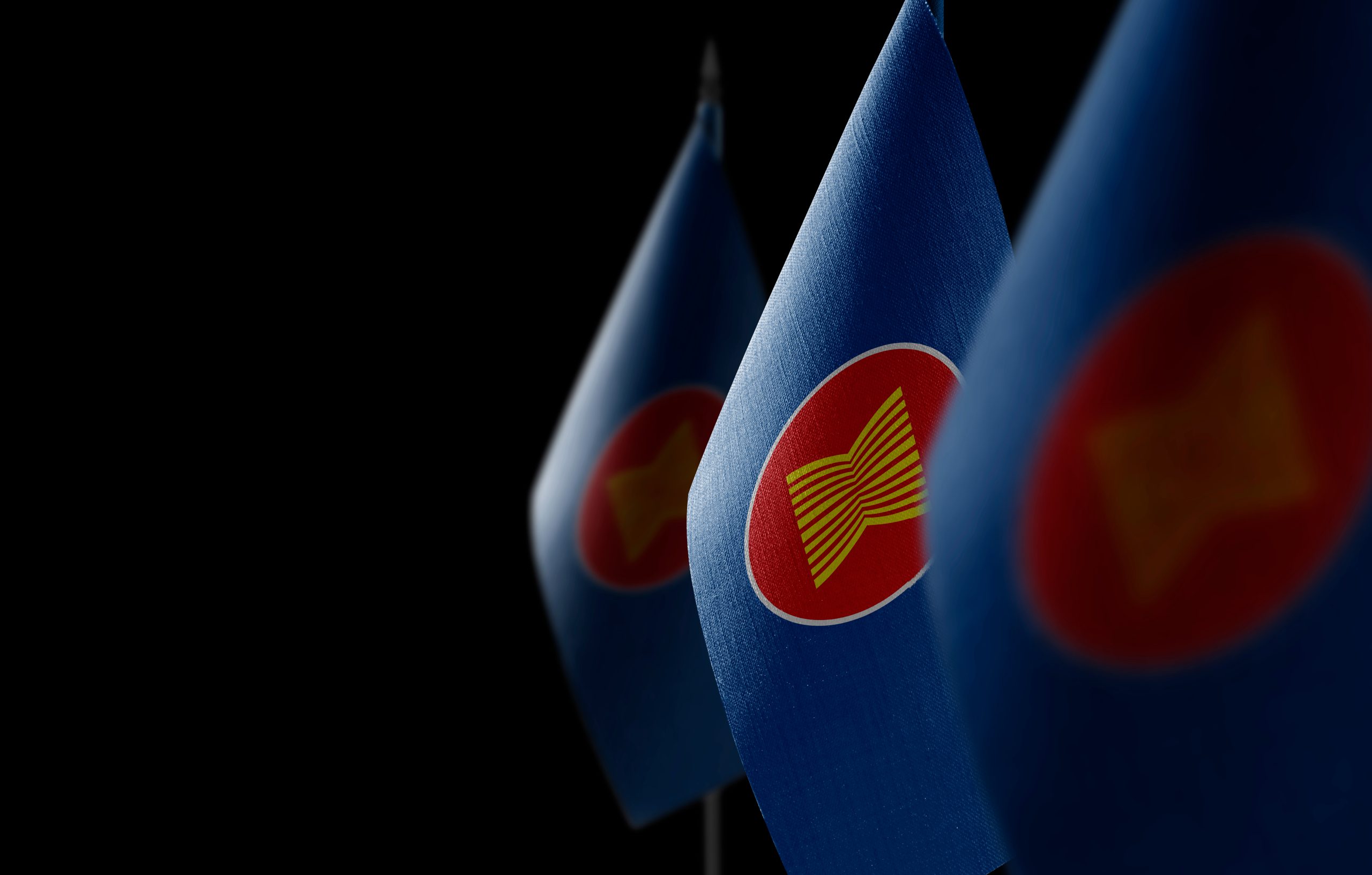出版物
アジアにおける国境を超える影響工作と人権への影響 [In English]
要旨2023年6月28日に一橋大学法学研究科の市原麻衣子教授が執筆した論文「アジアにおける国境を超える影響工作と人権への影響」がGlobal Asiaに掲載されました。本論文は、権威主義国家による越境的な影響工作、とりわけ中国のアジア諸国に対する工作の構造とその影響を解説しています。市原教授は、中国の影響工作の影響を最も多く受けている地域がアジアであると指摘しています。権威主義国家の影響工作が他国家の経済的不平等と政治的分断、そして市民の行動傾向を利用していると説明しています。また、諸人権を攻撃の的にしている影響工作は、権威主義国家内で発生している人権問題や政治的不安定性を隠すのが目的であると論じています。最後に、市原教授は影響工作に関する最先端の研究、ファクトチェック、カウンターナラティブの形成を通じた対抗手段の必要性を強調しています。
非承認国家の「民主主義」 ─その様相と規定要因─
要旨「非承認国家(unrecognized states)」は、「独立」を宣言し、国際的承認を得られないながらも事実上法的親国から独立した主体である。近年ではロシアによるジョージアやウクライナへの侵攻に際して、非承認国家やそれに類似する主体が出現し、その役割が注目されてきた。現存するその大半は競争的選挙を実施し、一部では選挙による政権交代も発生している。しかし、その多くは権威主義国からの支援で存立している上に、「民主化」しづらいとされる経済・社会的条件下にある。このため、一部の研究は、非承認国家特有の「民主化」要因が存在すると考えてきた。しかし、民主化指標によれば非承認国家の全てが民主化しているわけではなく、非承認国家の「民主化」度合いにはバリエーションがある。本論文では、非承認国家の政治体制の現状と関連する先行研究をレビューし、その課題を指摘した上で、新たな仮説の可能性を提起する。
日本の民主主義におけるデジタル分野課題への取り組みの漸進的な動き [in English]
要旨2023年4月28日に、法学研究科の市原麻衣子教授が執筆した論文、「日本の民主主義におけるデジタル分野の課題への取り組みの漸進的な動き」がAsia Democracy Research Networkから出版されました。本論文は、民主主義において必ずしもプラスに働くとは限らないデジタル技術に関する考察と、関連問題に対する近年の日本の取り組みを紹介しています。市原教授は、デジタル分野の発展は市民間不信、個人情報保護の侵害、そして政府による抑圧の容易化等の問題が発生していると指摘しました。これらの問題に対し、日本政府が輸出規制や人権に対するイニシアティブの発揮、偽情報に対抗するポジションの新設、ファーウェイへの規制等、諸処置に取り組んでいると説明しました。最後に、市原教授は偽情報が作り出すナラティブに対抗するナラティブが必要であり、そのためには権威主義アクターの戦略を特定した上でのナラティブ形成をすべきであると論じました。
ASEAN 5項目合意実行の失敗
要旨ミャンマーのクーデター指導者とASEAN首脳は、5項目について合意した。また、死者数、拘束者数、国内避難民数についても合意した。しかし、ミャンマー国軍、民族武装集団、人民防衛軍間の紛争は激化している。また、ASEANの一部の首脳は、ミャンマー国軍が人道的支援を国民に届かせないようにしていることから、ミャンマー国軍による合意履行プロセスは失敗だと言える。そのため、国際機関は、緊急に必要としている人々を支援するために声を上げた。合意から一年半が経過した今、ASEAN首脳は国軍による実施状況を検証し、ミャンマー国民の利益を尊重した有意義な行動を取るべき時である。
新興国取り込み、両刃の剣 G7サミット
要旨2023年5月22日に、朝日新聞にて法学研究科の市原麻衣子教授のインタビュー記事「新興国取り込み、両刃の剣 G 7サミット」が発表されました。本記事では、G7首脳会議で重要なテーマの一つとなったグローバルサウスと呼ばれる新興国・途上国との協調が論じられました。市原教授は、実利的で協調可能な議題を設定したことは、新興国や途上国への配慮を感じさせる一方で、G7はグローバルサウスを半ば強制的に「西側」に取り込むようにも見えるとしました。市原教授は、このやり方は賛否が分かれ、反発を買う可能性もあり、更に日本の関与により、日本は西側の一部と見なされることが増えると考えらえることから、グローバルサウスの取り込みには微妙なハンドリングが求められると論じました。
中国の技術、機会か危機か(スペイン語)
要旨2023年5月13日に、GGRアシスタントでチリの国際アナリストであるサッシャ・ハニグ・ヌニェズ氏の「中国の技術、機会か危機か(スペイン語)」と題された論考が、アルゼンチンの日刊紙『ラ・ナシオン』に掲載されました。ハニグ・ヌニェズ氏は、他の地域の事例を参考に、ラテンアメリカ地域諸国と中国のテック企業の連携について議論しています。まず、中国企業の特徴として、中国国内外を問わず、企業が収集した情報を中国共産党に対して提供する義務があることを挙げました。このため、ファーウェイやZTEは、情報セキュリティーに関する疑念を払しょくできず、オーストラリア、アメリカ、イギリス、そして日本などの多くの国で、国内ネットワークへの参加が禁止される事例が相次いでいると説明しています。一方で、ラテンアメリカ地域では、どの国家の企業を採用するべきかについて議論が続いていると指摘します。中国企業が価格やサービスにおける魅力を持っていることに加えて、中国政府のラテンアメリカ地域に与える影響力が増していることから、今後地域の政府が中国企業と連携する可能性は低くないと述べました。最後に、ハニグ・ヌニェズ氏は、中国のテック企業の進出に関する一国の決定は、ラテンアメリカ地域全体に影響を及ぼすと指摘し、地域枠組みレベルの議論が必要だと論じました。
ディストピア ―現実とフィクションの混合 [in Spanish]
要旨2023年3月20日に、GGRアシスタントで国際アナリストのサッシャ・ハニグ・ヌニェズ氏の論考「ディストピア ―現実とフィクションの混合」がスペインの文学批評ジャーナル『Cuadernos Hispanoamericanos』に掲載されました。ハニグ・ヌニェズ氏は、哲学、政治、文学などの資料を議論の出発点として参照しながら、研究分野、時代、地理を縦横無尽に越境し、ディストピアの概念について論じています。まず、J・S・ミルのディストピアの思想的淵源にT・モアのユートピア概念との共通性を発見します。また、権威主義政権における管理の経験がディストピア作品に反映されてきたと論じ、ソ連のY・ザミャーチンからチリのJ・バラディットまでにこの特徴を見出します。テクノロジーの発展は抑圧の手段をも発展させ、例えばクローン技術を取り入れたカズオ・イシグロの文学作品にも反映されていると指摘しています。最後に、ハニグ・ヌニェズ氏は、オーウェルが描いたような世界が現実で起こりつつあると述べるとともに、ディストピアが過度に使用されることは、鮮烈無比な意味を持つ言葉の陳腐化を招く可能性があると警句を述べました。
抑圧下の市民の声も聞いて 軽井沢でG7外相会合
要旨2023年4月16日の信濃毎日新聞に一橋大学大学院法学研究科教授・GGR研究員の市原麻衣子教授の記事「抑圧下の市民の声も聞いて 軽井沢でG7外相会合」が掲載されました。市原教授は、4月中旬より開催されるG7外相会合及びその後のG7サミットを見据えて、G7議長国として国際社会をリードしていくために日本政府が実施すべき政策の方針を述べました。まず、2023年3月20日に岸田首相が発表した自由で開かれたインド太平洋(FOIP)のための新たなプランにおいて中核として位置づけられている「自由」と「法の支配」の重要性を説き、その実現のためには「各国の歴史的・文化的多様性の尊重」が欠かせないと説明しました。一方で、相手国の文化の尊重には、単に相手国政府の主張を受け入れることだけではなく、相手国の市民の声にも耳を傾けることが要されると述べました。そのために必要となる民間アクターとの連携には、関連アクターが集まって立ち上げた「サニーランズ・イニシアティブ」と協働することが、日本政府にとって有効な手段となるとの見解を示しました。
2023年タイ総選挙 ―野党の台頭
要旨タイの総選挙が5月14日に実施される。クーデターを起こしたプラユット・チャンオチャ将軍(General Prayut Chan-o-cha)が率いる親軍政権に固執するのか、それとも別の道を歩むのか、タイ国民が決断するときが来た。親軍政党を優遇する非民主的な憲法にもかかわらず、最近の傾向では、2大野党であるプアタイ党(Pheu Thai Party)とタイ前進党(Move Forward Party)が地滑り的に勝利し、親民主的な連立政権が誕生する可能性がある。プアタイ党は、これまでの記録や最近の世論調査から、総選挙のたびに最多議席を獲得していることから、向かうところ敵なしといえる。今度の選挙でも勝利する可能性が高いと考えられる。一方、タイ前進党とその党首であるピター・リムジャルーンラット氏(Pita Limjaroenrat)の人気は、明確な政治姿勢、変化をもたらすことを望む印象的な政策、政策論争での卓越したパフォーマンスによって急上昇している。このような理由から、タイを軍事政権の遺産から救う、親民主的野党による新政権が誕生する可能性がある。
反目の歴史、対話重ねた先に ウクライナを積極支援するポーランド
要旨2023年3月22日、朝日新聞の「#論壇」というコラムにおいて一橋大学大学院法学研究科・GGR研究員の市原麻衣子教授が載せたコメントが紹介されました。教授がコメントをした記事はポーランド人が示したウクライナ人に対する手厚い支援を題材としています。この記事において、京都大学教授でポーランド近世史を専門としている小山哲教授がポーランドとウクライナの反目し合う歴史と対話を重ねてきた歴史を概説しています。そして、この対話の場があったからこそポーランド社会はウクライナ支援に熱心になることができると説明しています。論壇委員として市原教授はこの点を日本の平和主義と結びつけ、日本は自国の国境外のことに関しては関知しない姿勢を見せてきたと説明しています。また、平和な国際環境を形成するために積極的にこれに寄与すべきだと指摘しています。