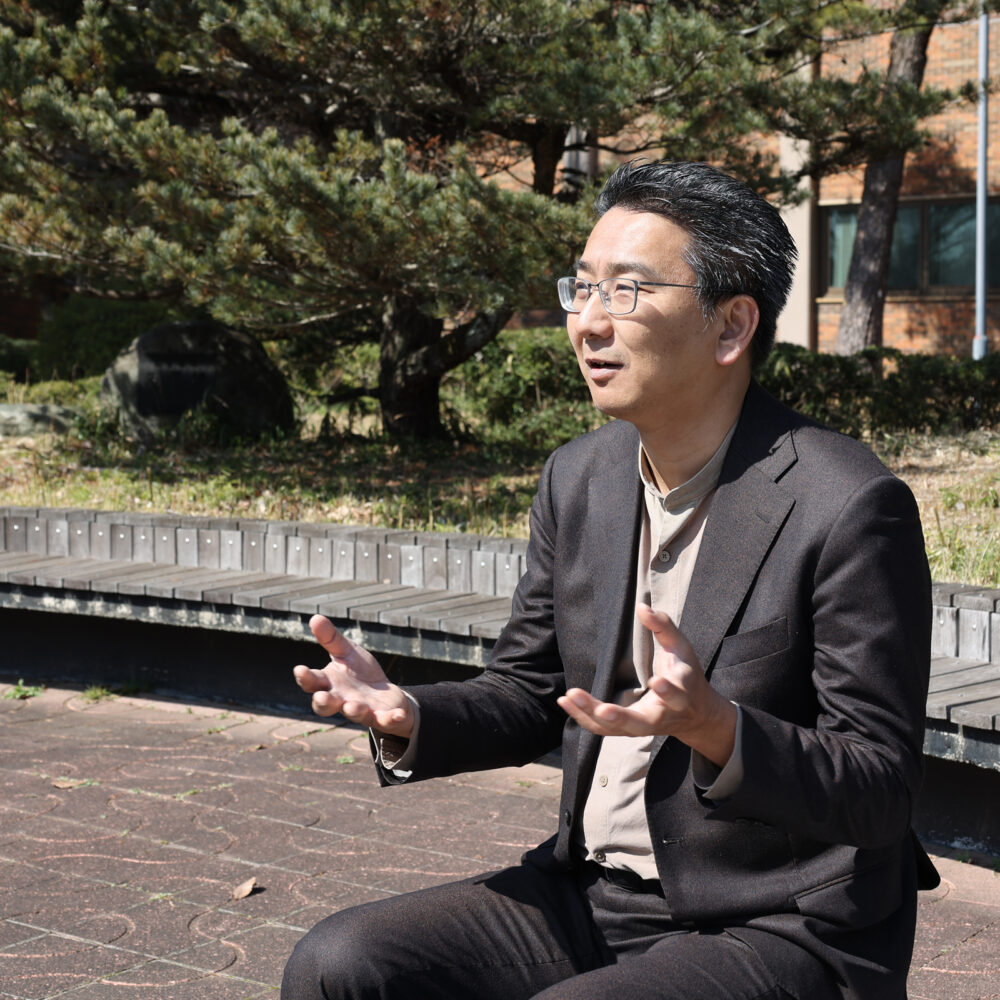私は東京に住むヤンゴン市民です
-ジャーナリスト北角裕樹氏インタビュー
聞き手・著者:チョン・ミンヒ
(一橋大学大学院法学研究科博士後期課程)
2024年4月25日
*本稿は、2024年3月11日に行われたインタビューをもとに作成された。
 北角裕樹さんにとって、東京は自分が異邦人かのように感じる場所のようだ。東京での人生に欠けているものがあるとすれば、それは何よりも日常を生きる感覚だ。会社でミャンマー人社員とともに働く充実した生活がヤンゴンにはあったと、クーデター前にヤンゴン在住のジャーナリストとして活動していた北角さんは言う。
北角裕樹さんにとって、東京は自分が異邦人かのように感じる場所のようだ。東京での人生に欠けているものがあるとすれば、それは何よりも日常を生きる感覚だ。会社でミャンマー人社員とともに働く充実した生活がヤンゴンにはあったと、クーデター前にヤンゴン在住のジャーナリストとして活動していた北角さんは言う。
しかし2021年、彼の仲間は他の都市に散らばり、刑務所に投獄され、あるいは永遠に会えない人となってしまった。北角さん自身も、ミャンマー国軍に2度にわたって投獄された。他の人たちに比べれば早く釈放されたが、生活基盤を奪われたまま日本に戻らなければならなかった。東京が見せる風景はヤンゴンとは何の関係もないものばかりで、どうしようもなく違和感をおぼえてしまう。
10年ほど前、彼はヤンゴンにもう少し住んでみようと慎重に考えた。日本経済新聞の記者として社会や教育分野の現場を経験した自分のことを、「リングのすぐそばにいながら、直接戦わない人」だったと振り返る。どのような試合をどれほど見てきたのかはわからないが、ある時から彼にも「リングで戦ってみたい」という気持ちが芽生えていた。会社を辞めた彼は、教育分野に身を投じるという挑戦をしたが、後に報道の世界に戻ることを決心した。
様々な国を旅して自分の舞台を模索していた2014年頃、滞在することになったのがミャンマーだった。ミャンマーで本当に選挙が行われるのだろうか、北角さんは関心を持った。現地で1年ほど編集関連の仕事をしながら、ヤンゴン大学のミャンマー語コースを2学期受講し、その後独立して自分の居住空間に小さな会社を設立した。
 民主主義に向かって一歩ずつ進むミャンマーの人々の生き生きとした姿と、人を驚かせるくらいの優しさに、初めは慣れなかったと話す。「たまたま携帯電話をタクシーに置いたまま降りると、お客さんが降りた場所に運転手さんが戻ってきて、ある外国人が近くで携帯電話をなくしたので探してくれないかと人に頼んでいくんですよ」。さりげなく助けるという行為が、彼らにとっては当たり前の発想であると理解するまでには時間がかかったが、北角さんは徐々に心を開いていった。
民主主義に向かって一歩ずつ進むミャンマーの人々の生き生きとした姿と、人を驚かせるくらいの優しさに、初めは慣れなかったと話す。「たまたま携帯電話をタクシーに置いたまま降りると、お客さんが降りた場所に運転手さんが戻ってきて、ある外国人が近くで携帯電話をなくしたので探してくれないかと人に頼んでいくんですよ」。さりげなく助けるという行為が、彼らにとっては当たり前の発想であると理解するまでには時間がかかったが、北角さんは徐々に心を開いていった。
ミャンマーの若者が映画界で自由に発言しはじめた頃、もっと具体的で明確な方法で彼らを応援したいと考えた。彼は地元の人々の生活にあまりにも近すぎて注目されない料理モヒンガを題材に、それを美味しく作り売ることで独裁者と戦う人物を主人公にした短編コメディ映画を制作した。彼の映画はニューヨークの映画祭で受賞し、脚本は日本語とミャンマー語の教育教材としても使われた。彼が持つ能力は、民主主義に向かうミャンマー人の夢を応援するために、一切の無駄もなくヤンゴンで発揮された。
北角さんは最近、タイを訪れていた。数週間滞在した後に日本に帰国した。本インタビューはそんな中で行われた。タイでは、日本全国から寄贈されたカメラや、人々が書いたメッセージカードとそれをミャンマー語に翻訳したものとをタイにいるミャンマー人たちに届けた。孤独な戦いに疲れ果てたジャーナリストたちに会い、彼らを覚えている人がいるということを伝えるたびに、北角さん自身の魂も励まされているような気がした。
北角さんは、物語が忘れ去られていくのを黙って見ているわけにはいかなかった。ストーリーを掘り起こし、人々の目に見えるようにする方法を彼は知っていた。ミャンマー人たちの喜び、挫折、喪失感、希望、大切な人たちとの最後の瞬間などを収めた短い映像に日本語と英語の字幕をつけ、オンラインプラットフォーム「ドキュ・アッタン(Docu Athan)」で公開し始めた。ミャンマーがいつ平和になるのかはわからない。平和になればすぐにでもヤンゴンに帰りたいと考えていた北角さんは、東京で何かを長期的にやろうという発想にはなれなかった。しかし、そんな彼にも心の故郷が必要だったのだろう。北角さんは、自分に勇気を与えてくれた現地の人たち、一緒に働けなくなった仲間たちとつながることのできる小さなプラットフォームを作り、そこで息を吸ったり吐いたり生活のリズムを取り戻しつつある。
東京の繁華街で、帰りたくても帰れない人々を見つめる。ミャンマーのために募金活動をしているボランティアを眺めながら、北角さんは、彼らが語らないこと、つまり募金活動が終わった後のことを頭の中で考える。お金を無事に届けるまでに、どれだけの苦労が必要となるだろうか。その過程において、多くの場合、関係する人々が苦心を重ねるものだが、こうしたことは人に知られていないのが常である。それでも彼らの努力を認めてくれる人がいることに北角さんは感心した。小学校2年生くらいだろうか、寄付をしようとする娘とその母親が交わした短い会話を北角さんは憶えている。
 「募金が本物かどうかわからないのに、本当にお金を寄付するつもり?」
「募金が本物かどうかわからないのに、本当にお金を寄付するつもり?」
「お母さん、あんなに一生懸命声出しているんだから、きっとお金は届けてくれるわよ」
募金は本物なのか、と時々尋ねる知人たちの警戒心は理解できる。しかし、北角さんは、何かを目的地まで届けることの大変さを分かった上で活動を続ける人々の気持ちを、もっと多くの人に知ってほしいと語る。
「ミャンマーの人たちは、困っている人のために自発的に声を上げてお金を集める活動を幼い頃から経験して育ちます。募金が終わったらお金を渡す人が必要であることも、そのプロセスが困難であることも知っています。信頼できる人を見つけるのは容易ではなく、その過程でコストが発生します。それほど簡単なことではないので、団体の活動によっては寄付が失敗することもあります。そういう過程を知っていても、ミャンマーの人たちは寄付をするんです。例えば、ある食堂に行って1,000円払ってチキンカレーを食べた、でも思ったよりおいしくなかったりする時もあるじゃないですか。だけど店員さんが優しいからまたそのお店に行こうと思うことがあるように、寄付も、あの人が頑張って声を上げているから1,000円出そうという風になればいいと思うんですよね」。
北角さんは責任の限界を既に超えて生きている人々の心の片隅に寄り添い、責任に線引きをする人々を目にする。何をやっても世の中は変わらないと諦めている人たちに、北角さんは、どんな状況でも自分を無力な存在としてみなさず、抵抗する術を失わずに生きている人たちがいることを伝えたい。彼は、ミャンマーで出会った親切な人たち――刑務所で数枚しかないTシャツをくれたり、掃除の仕方を教えてくれたり、差し入れで貰った奥さんの手作りの餃子を仲間に配ってくれたりした――に似た行いをしていた。
インセイン刑務所を去る際に、彼は刑務所に残っている人々と約束を交わした。彼らはこう言い残した。「例えば私たちが釈放されたとしても、この国がまだ独裁国家のままであれば、人々は自由に話すことができず、私たちは再び刑務所に戻らなければならないだろう。しかし、あなたの国は違う。君は戻って、私たちの代わりにミャンマーで起きていること、私たちの話をぜひ人々に伝えてほしい」。
ミャンマーに平和が訪れ、彼が再びヤンゴンに戻る日を期待しながら、インタビューを終えた。
*本インタビューのタイトルは、キム・リョンヒ氏の本「私は大邱に住む平壌市民です」から借りた。
ジャーナリストであり、ミャンマーのジャーナリストを支援するプラットフォームであるドキュ・アッタンの共同創設者。1975年東京生まれ。日経新聞社勤務を経て、2014年にヤンゴンに移住。2021年にはヤンゴンで2度拘束された。