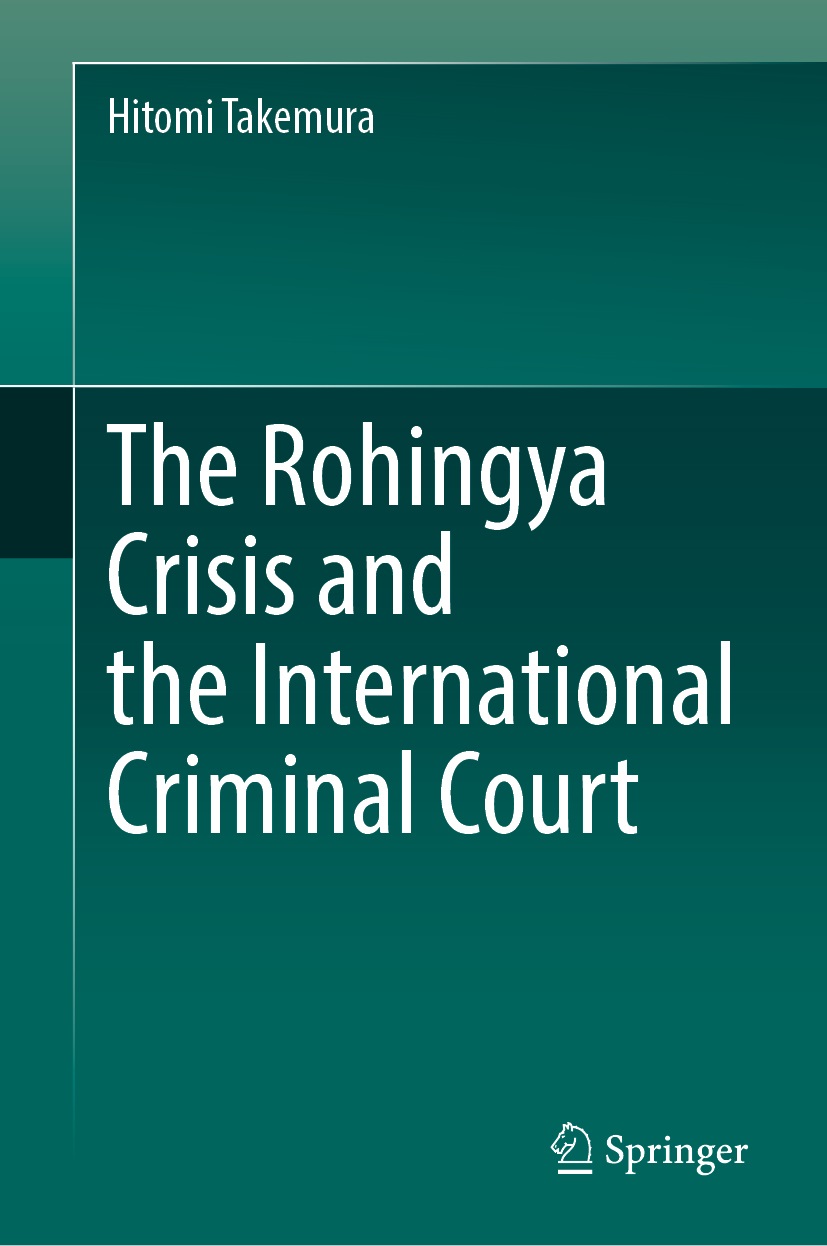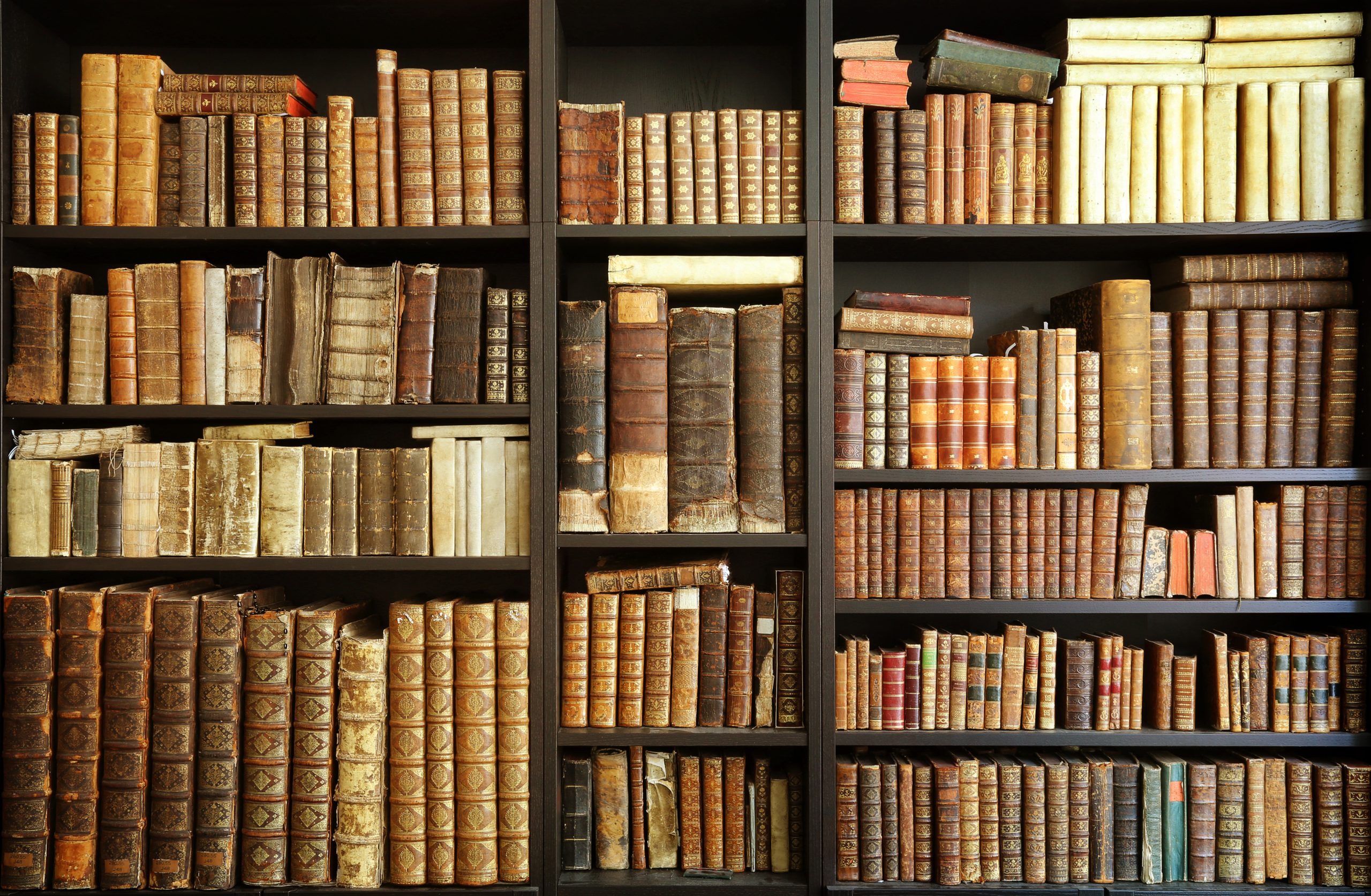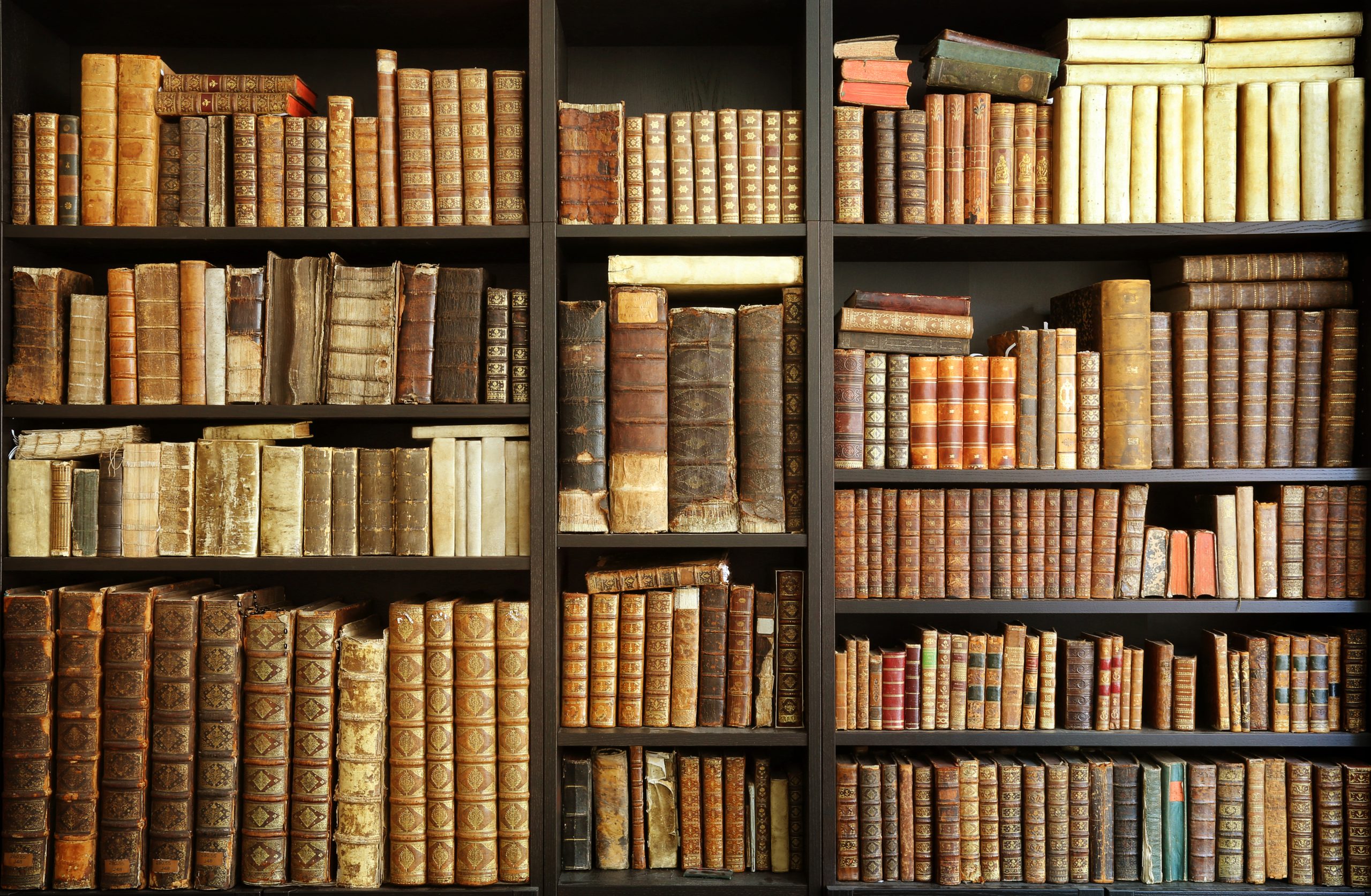その他の研究成果
ロヒンギャ危機と国際刑事裁判所 [in English]
要旨2023年5月31日に、一橋大学大学院法学研究科の竹村仁美教授の著書、『ロヒンギャ危機と国際刑事裁判所』がシュプリンガー社から出版されました。この書籍は、国際刑事裁判所(ICC)とロヒンギャ危機の関係を厳密に検証しています。本書は、特にICCとロヒンギャ問題との関連に焦点を当てながら、ICCの現代的課題を浮き彫りにしています。ミャンマーはICC規程の非締約国であることから、ロヒンギャ危機とICCの関係は複雑になっています。本書は、現在進行中のこの問題について最新の情報をもとに国際法の観点から分析を行うものです。竹村教授は、ロヒンギャ危機の歴史の説明、ロヒンギャ危機とICCの関係性、ICJのガンビア対ミャンマー事件とICCの進展との関連の議論などを本書で展開しています。そしてICCの正当性、実効性、効率性に関する最終的な評価に関しても議論しています。
EU予算保護のためのコンディショナリティ規則と法の支配
要旨2023年4月に法学研究科教授の中西優美子教授が執筆した論文、「EU予算保護のためのコンディショナリティ規則と法の支配」がEU法研究に掲載されました。本論文は、EU復興基金に関連し採択されたコンディショナリティ規則が法の支配の尊重を前提としている仕組みを問題視したポーランドの取消し請求に対する欧州司法裁判所(以下司法裁判所)の判断について解説しています。中西教授は、第2次法廷判決にあたる本判決で法の支配の遵守を義務付ける仕組みが設定され、司法裁判所がこの措置がEU法と合致すると判断したと確認しました。そのうえで、司法裁判所は法の支配を規定するEU条約2条を法的基礎とし、諸々の場面でその価値を保護する措置が必要であり、EU加盟国にはその価値を遵守する義務があると判断したと説明しました。更に、中西教授は、本件をEUのアイデンティティが何であるかを初めて司法分野で示した事例と評価し、今後法の支配を含む諸原則が司法判断の対象となりやすくなった点で、本判決のEU法発展における意義を大きく評価しました。
新興国取り込み、両刃の剣 G7サミット
要旨2023年5月22日に、朝日新聞にて法学研究科の市原麻衣子教授のインタビュー記事「新興国取り込み、両刃の剣 G 7サミット」が発表されました。本記事では、G7首脳会議で重要なテーマの一つとなったグローバルサウスと呼ばれる新興国・途上国との協調が論じられました。市原教授は、実利的で協調可能な議題を設定したことは、新興国や途上国への配慮を感じさせる一方で、G7はグローバルサウスを半ば強制的に「西側」に取り込むようにも見えるとしました。市原教授は、このやり方は賛否が分かれ、反発を買う可能性もあり、更に日本の関与により、日本は西側の一部と見なされることが増えると考えらえることから、グローバルサウスの取り込みには微妙なハンドリングが求められると論じました。
欧州連合法秩序の自律性と自律的な解釈 [in English]
要旨2023年2月に、Hitotsubashi Journal of Law and Politicsにて法学研究科教授でGGR研究員の中西優美子教授の論文、「欧州連合法秩序の自律性と自律的な解釈」が公表されました。本論文では、EU司法裁判所は、国際条約に関する裁判所意見等でEU法秩序の自律性を強調してきたのに対して、欧州人権裁判所の判決をEU法の解釈の際の基準として用いることは、EU法の自律性と矛盾しないか否かということが検討されている。本論文では、EU司法裁判所のEU法秩序の自律性にかかわる判例法を踏まえたうえで、EU基本権憲章52条3項により、EU司法裁判所は欧州人権裁判所の同一の解釈をすることを義務づけられているのかということを検討している。そのうえで、今後、EU基本権の発展させる、EU司法裁判所の自律的な解釈が重要であるとしている。
平和構築の理論と政策に対するマイクロ・エビデンス [in English]
要旨2022年11月30日に、一橋大学大学院法学研究科教授の大林一広教授が分担執筆した著書『平和構築の理論と政策に対するマイクロ・エビデンス』がシュプリンガー・ネイチャーで公開されました。本書籍では、複数の研究者がマイクロ・エビデンスに基づき、また内戦と市民の規範や価値などの要素も取り入れ、紛争後の平和構築の理論と政策に対する考察を行っています。大林教授が共著者と分担執筆した章では、パキスタン北西部地域における戦争による暴力とリスクや時間の選好、そして紛争後の社会政治組織への参加の関係を調査しました。戦争による暴力は被害者のリスク回避の傾向を高め、社会的活動に影響を与えることが研究結果から明らかになりました。一方で、地元の組織が安全網として機能する場合、この影響は軽減されることがわかりました。
欧州グリーンディールとEU経済の復興
要旨2023年2月28日に、一橋大学法学研究科教授の中西優美子教授が分担執筆した『欧州グリーンディールとEU経済の復興』が文眞堂から出版されました。本書は、EUのサステナブル・ガバナンスとして注目を集めている欧州グリーンディールの全体像を把握し、その基本構造を解説しています。中西教授が担当した第2章「欧州グリーンディールの法的基盤」では、欧州気候法を手掛かりに、欧州グリーンディールを理解する試みがなされています。中西教授は、欧州気候法を「最も厳格でかつ統一的な効果をもつ規則の形で採択」された法律と評価したうえで、実現に向けた措置を以下の3つに分けて解説しました。同法は、①拘束力のある目的設定、②期限の区分を設けた段階的な目標設定、③目標に向けた進捗状況の審査を通じて、法律で定める目標を達成する努力を明記しています。最後に中西教授は、同法に鑑みて、自然に還元するという認識が見受けられると述べつつも、自然を権利主体としていない現状に対して、抜本的な変化の必要性を指摘しました。
広島G7サミットと核軍縮―重要な議論、さらに求められることは(英語)
要旨2023年5月23日、国際・公共政策大学院長及び法学研究科教授でGGR研究員の秋山信将教授の論考「広島G7サミットと核軍縮―重要な議論、さらに求められることは(原タイトル:The Hiroshima G7 Summit and Nuclear Disarmament: Essential talks were held, but more is now needed)」が、ザ・ディプロマットに掲載されました。秋山教授は、G7サミットで発表された「核軍縮のための広島ビジョン」の位置づけやG7首脳が被爆地に立った意義について論じています。秋山教授は、核軍縮をライフワークとしてきた岸田首相が、広島でサミットを開催した意義を評価しました。さらに「広島ビジョン」は、厳しい国際環境にもかかわらず核軍縮を前面に立てたと論じ、既存の枠組みに則るだけでなく、透明性の向上といった点における新しいイニシアチブを打ち出したと指摘しました。最後に、グローバルガバナンスや核なき世界におけるG7の役割を強調し、国際社会は今回のサミットをより実質的な措置を実行するためのきっかけとするべきだと述べました。
G7核軍縮に関する広島ビジョン 異なる立場の対話尊重を
要旨2023年5月21日、東京新聞に国際・公共政策大学院長及び法学研究科教授でGGR研究員の秋山信将教授のインタビュー記事「G7核軍縮に関する広島ビジョン 異なる立場の対話尊重を 秋山信将・一橋大教授」が掲載されました。この記事は、G7広島サミットにおける核軍縮に関する議論が持つ課題について論じています。秋山教授は、広島サミットではG7の7カ国だけでなく招待国や国際機関も含めた形で、核軍縮への姿勢を示すことが重要だと説明します。また、現在の安全保障環境下でG7首脳が被爆の実相に触れる意義も指摘しました。最後に、首脳声明や広島ビジョンでは核拡散防止条約体制を堅持することが確認されたと指摘し、さらなる協調的施策が求められる中で、立場が異なる国々の対話の場を尊重することが核なき世界に近づく道だと論じました。
中国の技術、機会か危機か(スペイン語)
要旨2023年5月13日に、GGRアシスタントでチリの国際アナリストであるサッシャ・ハニグ・ヌニェズ氏の「中国の技術、機会か危機か(スペイン語)」と題された論考が、アルゼンチンの日刊紙『ラ・ナシオン』に掲載されました。ハニグ・ヌニェズ氏は、他の地域の事例を参考に、ラテンアメリカ地域諸国と中国のテック企業の連携について議論しています。まず、中国企業の特徴として、中国国内外を問わず、企業が収集した情報を中国共産党に対して提供する義務があることを挙げました。このため、ファーウェイやZTEは、情報セキュリティーに関する疑念を払しょくできず、オーストラリア、アメリカ、イギリス、そして日本などの多くの国で、国内ネットワークへの参加が禁止される事例が相次いでいると説明しています。一方で、ラテンアメリカ地域では、どの国家の企業を採用するべきかについて議論が続いていると指摘します。中国企業が価格やサービスにおける魅力を持っていることに加えて、中国政府のラテンアメリカ地域に与える影響力が増していることから、今後地域の政府が中国企業と連携する可能性は低くないと述べました。最後に、ハニグ・ヌニェズ氏は、中国のテック企業の進出に関する一国の決定は、ラテンアメリカ地域全体に影響を及ぼすと指摘し、地域枠組みレベルの議論が必要だと論じました。
核なき世界へ、たとえ遠回りでも 広島サミット、日本の研究者の期待
要旨2023年5月18日、朝日新聞に国際・公共政策大学院長及び法学研究科教授でGGR研究員の秋山信将教授のインタビュー記事「核なき世界へ、たとえ遠回りでも 広島サミット、日本の研究者の期待」が掲載されました。この記事は、「核なき世界」へ向けて、G7が発信すべき内容を論じています。まず、秋山教授は、大国間と地域における緊張の高まりを踏まえると、直線的な「核なき世界」への進展はおそらくないだろうと論じました。その上で、いかなる状況でも核兵器が最終的に使われなかったという実績を積み上げていくことは、遠回りで遅い歩みのように見えるものの、「核なき世界」の実現のためには大切なことだと述べました。また、核の分野において新興国と途上国との連携を強化するためには、各国が置かれている地政学的なリスクの相違に起因する、核兵器に対する認識の差を埋めることが重要だと強調しました。加えて、中国の保有する核兵器については、情報開示が乏しいことから、透明性の面で大きな問題があると説明しました。