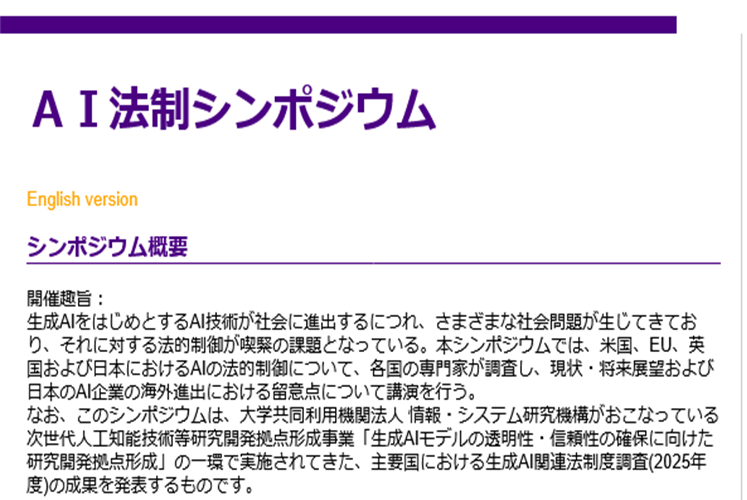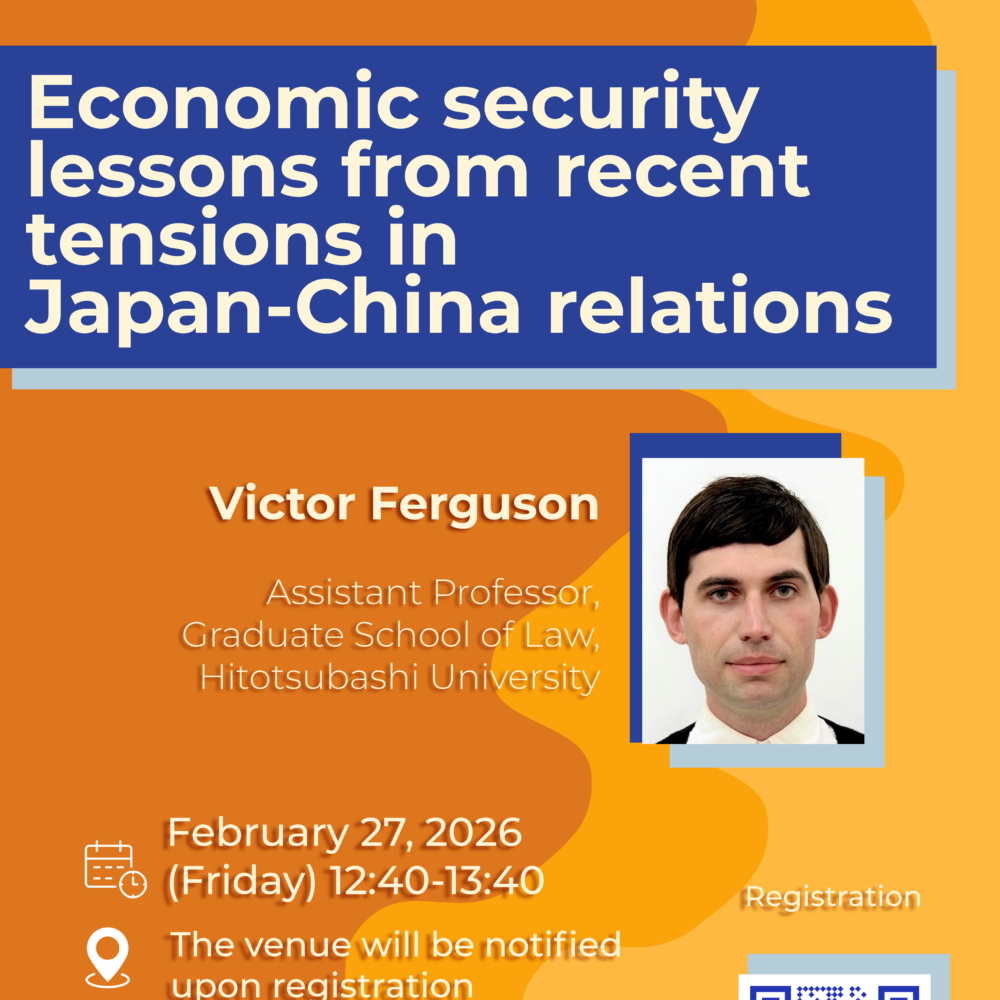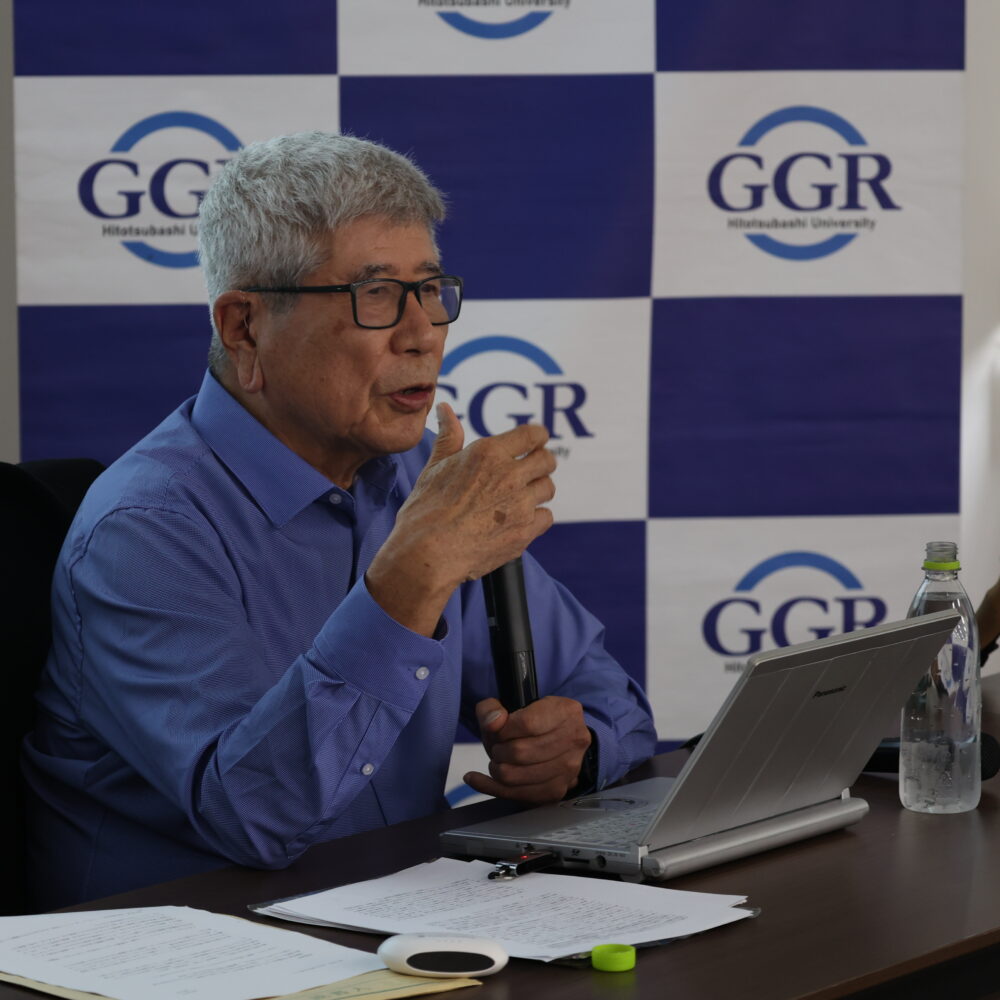ニュース
民主主義・人権プログラム
「トランプ米大統領『まだ多くの標的残っている』 イラン空爆巡り演説」へのコメント
2026年2月26日
2025年6月22日、朝日新聞の記事「トランプ米大統領『まだ多くの標的残っている』イラン空爆巡り演説」に対する市原麻衣子教授(法学研究科)のコメントが公開されました。本記事は、イランの核施設に対する空爆に関し、トランプ米大統領が21日にホワイトハウスで国民向けに行った演説の内容を報じています。市原教授は、近年、国際秩序を支えてきた主権規範、不戦規範、人権規範が大国により挑戦され、脆弱化していると指摘しています。帝国主義への逆行を防ぎ秩序を取り戻すため、欧州諸国および日本が積極的な外交を行うべきだと述べました。
民主主義・人権プログラム
「国民民主、山尾志桜里氏の公認見送り 疑惑巡り会見するも批判が噴出」へのコメント
2026年2月16日
2025年6月11日、朝日新聞に掲載された「国民民主、山尾志桜里氏の公認見送り 疑惑巡り会見するも批判が噴出」に対する市原麻衣子教授(法学研究科)のコメントが公開されました。本記事は、国民民主党が同日の両院議員総会で、参院選全国比例に立候補予定だった元衆議院議員・山尾志桜里氏の公認を見送ると決定したことを報じています。市原教授は、山尾氏の不倫疑惑は公認内定前から知られており、玉木代表にも同様のスキャンダルがあることから、今回の公認見送りは不倫そのものではなく、党が新たに獲得したソフト右派層の批判が想定を上回ったためではないかと指摘しました。また、不倫に対する社会的批判が男女で不均衡である点、今回の対応がその風潮を容認するメッセージとなりかねない点にも懸念を示しました。
「コンテンツコントロールと権威主義的地域主義」への出演(英語)
2026年2月16日
2025年4月24日、YouTubeにフロンク・ダニエラ講師(社会科学高等研究院)が出演したGlobal Governanve Programme EUIの動画「Content control and authoritarian regionalism | Danielle Flonk and Stephanie Hofmann」が公開されました。動画においてフロンク講師は、中国やロシアといった権威主義国家が、国際機関を通じてどのようにデジタル秩序を形成しているのかを解説しています。フロンク氏は、中国やロシアの狙いはインターネットガバナンスをマルチステークホルダー型の場から、自らがより大きな影響力を持つ政府間組織へと移行させることであり、「サイバーセキュリティ」よりも「情報安全保障」を重視していると述べました。また、両国には検閲やデジタル統制の規範を輸出するため、地域的な同盟や国際フォーラムに多大な投資を行っているという共通点があることを指摘しました。
民主主義・人権プログラム
「平野レミさんが語る平和と料理 米兵の子、放っておけなかった父親」へのコメント
2026年2月10日
2025年6月8日、朝日新聞に掲載された「平野レミさんが語る平和と料理 米兵の子、放っておけなかった父親」に対する市原麻衣子教授(法学研究科)のコメントが公開されました。本記事は、戦後80年を記念し、料理愛好家・平野レミさんが、仏文学者で詩人の父・威馬雄(いまお)氏について語ったものです。威馬雄氏は終戦後、米兵と日本人女性との間に生まれた子どもたちを支援した人物として知られています。市原教授は、見ず知らずの子どもたちを自宅に迎え入れ、親身に接した威馬雄氏の姿勢に敬意を表し、他者とのコミュニケーションのハードルを下げ、他者との関係性を大切にし、利他的に行動できる人が増えることが、より温かな社会の形成につながるのではないかと述べました。
民主主義・人権プログラム
『誰も暴動は望んでいない』止めに入る参加者 ロス抗議デモの現場」へのコメント
2026年2月2日
2025年6月10日、朝日新聞に掲載された「『誰も暴動は望んでいない』止めに入る参加者 ロス抗議デモの現場」に対する市原麻衣子教授(法学研究科)のコメントが公開されました。本記事は、不法移民の一斉摘発をきっかけに米カリフォルニア州ロサンゼルスで発生した抗議デモの様子を報じたもので、トランプ政権による州兵派遣がさらなる反発を招く一方、参加者同士が平和的な抗議を呼びかけ合う動きも見られたとしています。市原教授は、2019年の香港における反逃亡犯条例デモを引き合いに出し、全米の分断と混乱を狙う勢力が、抗議者を装って暴力を行使する可能性を指摘。そうした事態をあらかじめ想定し、決して同調せず、冷静に対処する耐性を養うことが重要だと述べています。
民主主義・人権プログラム
「『ばかたれ』『国民心理を逆なで』農家らが憤り、農水相コメ発言で」へのコメント
2026年1月26日
2025年5月19日、朝日新聞の記事「『ばかたれ』『国民心理を逆なで』農家らが憤り、農水相コメ発言で」に対する市原麻衣子教授(法学研究科)のコメントが公開されました。本記事では、江藤拓・農林水産相(当時)が18日に「コメは買ったことがない」などと発言したことに対する、農家や消費者からの憤りや反発の声が報じられています。市原教授は、米価格の高騰により、こども食堂やホームレス支援団体などが配給の困難に直面している現状に言及し、江藤元大臣に対して辞職にとどまらず、こうしたボランティア団体への米の寄付を検討すべきではないかと提言しました。
グローバルリスク・危機管理プログラム
イランは進めるも引くも地獄 秋山信将・一橋大教授の見方
2026年1月23日
2025年6月16日、秋山信将教授(法学研究科)がインタビューを受けた朝日新聞の記事「イランは進めるも引くも地獄 秋山信将・一橋大教授の見方」が公開されました。本記事は、イランの核開発問題をめぐって米国とイランが継続してきた高官協議の第6回会合が中止されたことを受け、交渉の行方について秋山教授にインタビューしたものです。秋山教授は、イスラエルによる攻撃を受けた現状では、イランが米国の求める核開発計画の全面放棄の条件で交渉に応じる可能性は低く、交渉を進めても引いてもイランにとっては困難な状況であると指摘しました。
民主主義・人権プログラム
「退職したいほど『電話が怖い』 SNS世代の社員が抱く不安と責任感」へのコメント
2026年1月23日
2025年5月12日、朝日新聞の記事「退職したいほど『電話が怖い』 SNS世代の社員が抱く不安と責任感」に対する市原麻衣子教授(法学研究科)のコメントが公開されました。同記事では、SNS世代が電話対応に対してプレッシャーや苦手意識を抱く背景について、当事者や専門家への取材を通じて分析しています。市原教授は、人にはそれぞれ苦手なことがあると理解を示した上で、職場での電話対応に関しても、若者が無理のない範囲で社会生活に適応できるような環境づくりが重要だと述べました。たとえば、電話対応の負担が一人に偏らないような配慮が必要ではないかとしています
民主主義・人権プログラム
「デンマーク、米大使代理を召喚 グリーンランドで諜報強化の報道受け」へのコメント
2026年1月20日
2025年5月9日、朝日新聞の記事「デンマーク、米大使代理を召喚 グリーンランドで諜報強化の報道受け」に対する市原麻衣子教授(法学研究科)のコメントが公開されました。同記事では、トランプ米政権がデンマークの自治領であるグリーンランドにおける諜報活動の強化を命じたとの報道を受け、デンマーク外務省が駐デンマーク米国大使代理のゴッドフリー氏を召喚し、説明を求めたと報じられています。 市原教授は、仮にトランプ政権がグリーンランドの独立運動に関する諜報活動を行い、それをもとに独立運動を煽る影響工作を企図しているのであれば、それはロシアや中国による影響工作と同様の手法であり、看過できないと指摘しました。
グローバルリスク・危機管理プログラム
イスラエルが再び攻撃 イラン核施設内部では汚染発生か
2026年1月15日
2025年6月13日、秋山信将教授(法学研究科)がインタビューを受けたNHKの記事「イスラエルが再び攻撃 イラン核施設内部では汚染発生か」が公開されました。本記事は、同日イスラエル軍がイラン各地の核関連施設など100以上の標的を攻撃したと発表したことを受け、被害状況や各国の反応、経済への影響などを報じています。秋山教授は、今回の攻撃はイランの核プログラム全体の破壊を狙った可能性があると指摘しています。そのうえで、イラン側がこれを国家全体への攻撃と受け止め、核兵器の必要性を改めて認識した可能性があると述べ、武力行使のさらなる拡大への懸念を示しました。